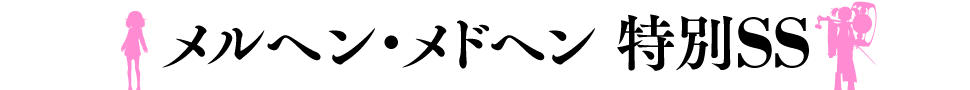『彼女の怠惰を阻むもの』
加澄有子は怠惰と怠慢と退屈を信条としている。
面倒なこと、厄介なことは可能な限り避けたい。
一日中寝転がって自堕落に過ごしたい。
平穏で平和な人生をおくりたい。
だが、そんな有子の願いとは裏腹に、この世界には彼女の怠惰を阻むものが多すぎる。
加澄有子は常々そう感じていた。
「加澄さん、加澄有子さん!」
唐突に眠りの世界から引き戻され、有子はぼんやりとしたまま顔をあげた。
「加澄有子さん、授業中に寝るとは何事ですか」
「寝てません」
有子はウソをついた。バレバレのウソであろうとも絶対に譲らず針のようにただ一点のみ貫けば押し通せる。……こともある。
面倒なことを避け、あらゆる労力という労力を惜しむ有子が見出した一つの真理だった。
だが、残念ながら今回は相手が悪かった。
「そのような適当なウソが通じると思ったら大間違いですよ。さあ、今の続きから読んでみなさい」
寮母兼教師の白銀先生は老齢とは思えない鋭い視線で有子の企みを一蹴する。
規律規範規則を何よりの信条とする白銀先生は怠惰怠慢退屈を愛する有子にとってまさに正反対の存在。ある意味で天敵とも言えた。
「だいたい、加澄さんはメドヘンとしての自覚が足りません。あなたを選んだ『一寸法師』という『原書』は、日本に古来より伝わるものなのです。たとえば先代の契約者は――」
長い長いお説教がはじまった。
途中で居眠りすることも視線を逸らすことも許されない。心を無にして聞き流していてもすぐにバレてしまう。有子にとってそれはまさに地獄のような時間だった。
「このように、長い歴史の中で数多の『原書使い』の手に渡り、その都度この国を……いえ、世界を守ってきたのです。あなたはそんな先人に恥じぬよう日々、努力と研鑽を重ね卒業したあかつきには立派な原書使いとして……聞いていますか!? 加澄有子さん!」
「うう……」
面倒くさい……。
有子は心の中でぼやいた。
「世の中はちょっと面倒なことが多すぎると思う」
休み時間。有子は同じクラスの静の元にやってくると、いつになく力のこもった口調でそう告げた。
「突然、なんですの。まさか、わたくしに同意を得たいだけとか言いませんわよね」
「違う。もっと大事なこと」
次の授業の準備をしながら半眼で見上げる静に、有子はずずいっと顔を寄せる。
「わたしたちはメドヘン」
「そうです。なにをいまらさら確認する必要がありますの?」
「つまり、戦うのが仕事」
「仕事かどうかはともかく、大切なお役目の一つですわね」
「ヘクセンナハトももうすぐ。今から準備しないといけない」
「……まあ、その通りです」
「よって、補習は受けなくていい」
「ちょっとお待ちなさい加澄さん!」
うんうんと納得したとばかりに頷いて去ろうとする有子の裾を静が掴んだ。
「まったくこれっぽっちも理屈が成り立ってませんわよ。だいたい、そうやって補習をサボる口実にわたくしを巻き込まないでください。白銀先生に口添えなんてしませんわよ」
「ちっ……」
勘のいい静に思わず舌打ちをする。
静も付き合いが長いだけあって、有子の考えそうな屁理屈の類にはすぐに気づくのだ。
「そう言わずに、一緒に叱られよう」
「なぜわたくしまで叱られなければなりませんの!?」
「それはほら、同じチームメイトとして」
「チームメイトだからと言って、そこまで一蓮托生になりたくありませんわよ!」
「そんな、病める時も健やかなる時も一緒と誓ったのに」
「誓ってません。だいたい、それは結婚の時の文言です」
「がーん。価値観のズレ……すれ違いの生活……冷めきった関係……静とはここまでみたい。実家に帰らせていただきます」
「なにをバカなことを……。その実家もほとんど同じようなものでしょう」
ちなみに、静の土御門家は京都に広大な土地の大邸宅を構えている。その土御門家の分家筋にあたる有子の加澄家も同じ敷地内にあった。
「えー……補習めんどくさい」
「結局、それが本音ですわね」
世の中には面倒なことが多すぎると有子は常々思っている。
授業だとか補習だとか、それから家のこととか。
魔法使いの家系というのは、とかく面倒なしきたりや慣習が多い。とくに土御門家くらいの名門となると並大抵ではない。
静と有子は遠縁とはいえ親戚同士でおまけに同じ敷地内に住んでいるというのに、実のところつい最近まで言葉を交したことすら数えるほどしかなかったのだ。
分家のそのまた分家という外様な加澄家にとって土御門の次期当主である静はまさに雲の上の存在で、間違っても友達とかそういった気安い相手ではなかった。
自分たちは土御門家のためにその身を捧げるのだと、有子は幼い頃から言い聞かされて育てられてきた。まったく時代錯誤な話だった。
物心ついてすぐから厳しい訓練を強要されてきた有子は、自然とそんな家同士の関係や古い慣習に反発を抱くようになっていた。
特別なものなどいらない。自分がほしいのは柔らかい布団とか、ポカポカするような陽気だとか、そういうのだ。そう信じて疑わなかった。
だが、有子は土御門静と出会ってしまった。
大勢の付き人を従えて大廊下を歩く静の姿は誰よりも美しく、それこそ物語の中から出てきたお姫様か女神に見えた。
彼女を守るのが自分の役目だと思うと、それはなにか特別なことのように感じられた。
面倒なことを避けたい有子が、土御門家次期当主の護衛というとてつもない面倒ごとを自ら引き受けたいと、そう思ってしまった。
また、有子の不運はそれだけにとどまらなかった。
それは『原書』に選ばれてしまったことだ。
原書『一寸法師』は長くひとりの『原書使い』と契約していた。彼女が“上がり”の日を迎えて『一寸法師』の原書を原書図書館に返却をすることになったその日に、有子を新たな契約者として選んだ。
『原書』と契約することは魔法使いにとっては大変な名誉である。それこそエリートコースに乗ったようなものだ。
いまいちぱっとしない傍流の分家から誕生した期待の星。しかも次期党首の土御門静と同い年ということになれば、様々な面で当主を助ける重職につくのは間違いない。
有子の両親はもちろん、分家の一族郎党が大喜びした。
こうしてまた有子は面倒ごとを一つ抱えてしまった。
時が経ち、やがて有子は静と共にクズノハ女子魔法学園に入学する。
「学園にいる間は本家と分家は関係ありません。お互い、いち生徒。対等な関係ですわ」
入学してすぐ、静は有子にそう言った。
静は、案外普通の女の子だった。それでも幻滅するようなことはなかった。
なぜなら静もまたずっと有子のことを見ていたからだ。あの広大な屋敷で唯一無二とも思える同い年の女の子は静にとっても特別気になる存在だったらしい。
有子はまた面倒ごとを抱えてしまった。
相手は雲の上の存在だ。気安く接したりできるわけがない。なのに“普通にしろ”とそんな面倒なことを強要するなんて。
悩んだ挙げ句、有子は静との関係を近くて遠い“幼馴染み”ということで自分を納得させることにした。
こうして、今の静と有子のつかず離れずな関係がはじまった。
「もう、仕方ありませんわね……」
有子が昔のことに思いを馳せていると、ふいに静が立ち上がる。
「静、どこ行くの?」
「白銀先生のところです。わたくしが一緒に謝って差し上げます」
溜息をつきながら静は言った。
「さすが、静大好き」
「別に、加澄さんのためじゃありません。ヘクセンナハトも近いことですし、訓練の時間を減らしたくないだけですわ」
ぷいっと顔を背けると静はひとりでさっさと先に行ってしまう。
“あの子”が来てから静は少し変わった。
土御門家の当主ではない、ただの“静ちゃん”の顔を見せるようになった。
そのことが有子には嬉しくて……でも、少しだけ複雑でもある。
「ほら、早く行きますわよ。でないと休み時間が終わってしまいます」
「ん、すぐ行く」
有子は静の後を追った。
加澄有子は怠惰と怠慢と退屈を愛している。
面倒なことはしたくない。
だが、この世界には彼女の願いを阻むものが多すぎる。
たとえばそれは、つまらない授業だったり、やたらと厳しい先生だったり、魔法使いの家系だったり。
そして放っておけない幼馴染みだったりするのだ。