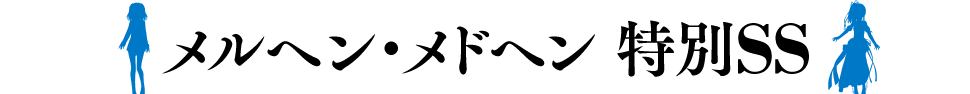『葉月のお友達メモ その3 メドヘンのお仕事』
『メドヘン』とはなんなのか。
自分が『シンデレラ』に選ばれた『メドヘン』であると言われても、いまいちピンとこない私こと鍵村葉月は、自分で考えるのを早々に諦めて魔法学園の人たちに聞いてみることにした。
下手な考えは時間の無駄というか、私のことだからきっとすぐに妙な方向に思考が脱線してしまうに違いないと思ったからだ。
というわけで、最初に相談してみたのは――
「ほう、メドヘンとはなにか……と」
学園長さんは私の質問にスッと目を細める。
「メドヘンである君がメドヘンについての説明を他者に求めるのか……ふむ、己を知ろうとする時、得てして人は自らの内側に答えを求めようとする。だが、真の自分とは他者の中にこそあるのかもしれない。ふむ、実に興味深い質問だ」
あ、これめんどくさいやつだ。
私は直観的にそう思った。
「あ、やっぱりいいです。学園長さんお忙しそうなので……」
「待ちたまえ鍵村葉月」
私の肩を学園長さんの手がぐわしっと掴む。
かぎむらはづきはにげだした! しかし、まわりこまれてしまった!
「私の仕事については気にする必要はない。いざとなれば二、三人ほど自分を増やせばいいのだから」
なにを言っているのかいまいちわからなかったが、そういうことらしい。私は諦めて学園長さんの話を聞くことにした。
「メドヘンとは何か、だったな。実のところ、私もずっと以前からその疑問を考え続けている。メドヘンはなぜ存在するのか、なんのために生まれてくるのか……と。そして一つの答えに辿り着いた」
遠い目をする学園長さん。できればあまり難しい話にならないことを願うばかりだ。
「その答えとは、すなわち――“分からない”だ!」
「は……?」
「考えてもみたまえ、メドヘンが存在するのは原書があるから。その原書は物語から生まれ、物語は言語、言語は文化、文化は人から生まれる。遡ればそもそもなぜこの地球上に人間が、生き物が生まれたのかということに行き着いてしまう。考えても答えなど出ないのだよ」
うーん、なんだかもの凄く誤魔化されたような……。
「というわけで、我々のようなただの人間には身に余る答えだ。もちろん、もっと別の切り口から――たとえば哲学的な観点からの考察もできるが、その場合は一晩や二晩は徹夜する覚悟をしてもらわねばならんが?」
「い、いえ! も、もも、もう充分です!」
そんなに長い間、学園長さんの話に付き合っていたら頭が爆発してしまう。
もっと別の人に聞くことにしよう。
「そうだ。もし、歴史的な意味ということであれば白銀先生に聞くといい」
学園長さんは、立ち去る私に向かって言った。
学園長さんのアドバイスに従って私はさっそく白銀先生のもとにやってきた。
白銀先生は真っ白な髪をぴっちり後ろでひっつめた初老の女性教師だ。魔法学園では寮母と、歴史や行儀作法などを担当しているちょっぴり怖い先生だ。ちなみに私はその見事な白髪といつもピシッとした雰囲気からミズ・ホワイトと呼んでいる。もちろん心の中で。
「メドヘンとは何か……その質問は少々具体性に欠けますね」
「はい……すみません」
さっそくお小言をちょうだいしてしまう。
「メドヘンという言葉の本来の意味であれば“乙女”や“少女”というのが正しいでしょう。これは『原書』が選ぶのが必ず十代の若い娘であることからそう呼ばれるようになったそうです」
「へぇ……じゃあ、男の人とか大人の女性はいないんですか?」
「ええ。『原書』と契約した男性は今のところ一人もいません。ですが、大人の女性はいます。彼女たちは十代の頃に『原書』と契約しそのまま大人になった方々です。私もその一人です」
つまり、契約できるのは十代だけど手放しさえしなければ大人になってもメドヘンでいられるってことかぁ。
「その後、強大な力を持つメドヘンには魔法学園で力の扱い方とそれを持つに相応しい正しい心を身につけることが義務付けられたことで、卒業前の見習いたちを『メドヘン』と卒業を認められ一人前になった者を『原書使い』と呼ぶようになりました」
「なるほど。そうですよね、おばさんやおばあちゃんになってまで“少女(メドヘン)”って呼ばれるのはさすがに痛いというか……」
ハッと気づけば、ミズ・ホワイトこと白銀先生がもの凄い目で私を見おろしていた。
「鍵村さん……あなたは目上の人間に対する礼儀を学ぶ必要があるようですね」
ひいいいいいっ!
白銀先生にこってり絞られたことで今度は同じメドヘンの人たちに話を聞いてみることにした。微妙な年齢の方々に、この話題はセンシティブすぎると教訓を得たからだ。
そんなわけで、最初に声をかけたのは……
「メドヘンについて聞きたいって? 今さらな話だなぁおい」
カザンさんは少し呆れたように苦笑いする。
「戦う。そんだけだ」
あまりにもカザンさんらしい簡潔な答えだった。
「も、もうちょっと具体的にお願いします」
「他に何があるってんだ。魔法学園にいる間はメドヘン同士で戦って、卒業した後は魔法獣どもと戦う。そうやって死ぬまで戦うのがアタシらの仕事だ」
カザンさんはどこか達観したように言う。
それが彼女にとってのメドヘンというものらしい。
「考えてもみろよ、アタシらは『原書』と契約するとそれぞれ特別な力――固有魔法を使えるようになるが、そいつは必ず戦いのための魔法だ。あ、いや、おまえと『シンデレラ』は例外な。いろいろ非常識すぎる」
非常識と言われてしまった。
「たとえば、アタシの『酒呑童子』は雷の力を操る。だけど、そのままじゃちっとばかり使いづらいからこうやって“太刀”のかたちにして制御するんだ」
カザンさんの手の中に大きな刀が現われる。片刃の大太刀は確か“大蛇”という名前だったと思う。
「だけど、こうやってめいっぱい制限してもできることといえば“斬る”か“叩きつける”くらいのもんだ。そんくらいにしか使えねぇ。要するに、なんかをぶっ壊すくらいしか使い道がねぇんだ」
「だから、戦うための魔法……?」
「ま、そういうこった」
カザンさんはあっさりと言う。
私みたいにいろいろ悩んだり迷ったりしてないみたい。
もしかすると、わざと考えないようにしてるのかもしれなかった。
次は誰に話を聞こうかなと思いつつ探していると、ちょうど裏庭でサボって物思いに耽っている加澄さんを見つけた。
「加澄さん!」
「……んあ?」
どうやら寝てたらしい。半分開いた口からちょっとヨダレが……。
「……なに? 用事?」
「えっと、ちょっとお話聞きたいなって」
ぐしぐしと目をこする加澄さんに、私はいろんな人に「メドヘンとはなにか」を聞いて回っていることを伝えた。
「メドヘンとは……さあ? 考えたこともない」
加澄さんはいつものようにめんどくさそうに答えた。
「なんか、実家の蔵にコレがあった。触ったらぴかーって光って契約してた。おしまい」
加澄さんの手に『一寸法師』の原書が現われる。私の『シンデレラ』とよく似た分厚いハードカバーの本だ。これが私たちメドヘンの力の源なんだけど、見た目にはただの古い本にしか見えない。
「おしまいって……そ、それだけ?」
「そう。契約したらメドヘンとしてここに通わなきゃいけなかった。あとは、まあ、実家のしがらみとかいろいろ。逆らってもめんどくさいからテキトーに流れに任せて……」
そう言って、加澄さんはあくびを噛み殺す。
「原書と契約できた人間は、魔法使いの中でも特別だから。出世街道まっしぐらでエリートコース。……まあ、卒業できたらだけど」
うーん、要するにくじ引きだけでいい大学に入学できてしまったような感じだろうか。
「あたしとしては、もっと楽に生きたい。戦うの、めんどくさい……不労所得……印税生活……楽して生きる……ふにゅう……」
「か、加澄さん?」
返事がない。どうやらまた寝てしまったらしい。
その後も何人かに同じ質問をしてみたけど、みんなバラバラ。
というかメドヘンになったことはあまり重要じゃなくて、メドヘンの力が自分の目的の近道になると考えているようだった。
その目的っていうのも、カザンさんと加澄さんではまるっきり違う。
「けっきょく、メドヘンってなんなんだろう……」
私にとってのメドヘンは、魔法少女で変身ヒロインで能力バトルもの? って感じ。
だけど、恐ろしいモンスターが毎週現われて街を壊すわけでもなく宿命のライバルみたいな相手がいるわけでもない。
それ以前に、私はまだきちんと魔法が使えるようになっていない。
「魔法が使えるようになったら何か見えてくるのかなぁ」
そうやって、ぼんやり考えていると「葉月さん」と、誰かが私を呼んだ。
「こんなところにいましたのね。体育館にいらっしゃらないので、探しましたわ」
「あ、静ちゃん! ご、ごめん!」
たいへんだ。いろいろ悩みすぎて練習の時間過ぎちゃってた。
「時間のことはかまいませんが、それよりなんだかお元気がないような……もしかして、体調が悪いのですか? でしたら、今日の練習はお休みにして」
「ううん! そんなことないよ! ただ、ちょっと、悩んでるというか……」
「悩み、ですか?」
私は今日一日、いろんな人に聞いたことについて静ちゃんに話した。すると静ちゃんは少し困ったような顔で。
「それは難しい疑問ですわね。魔法使いと言っても、普通に生きて暮らす人間ですから、葉月さんがいた“あちら側”とそう変わりはありません。とくに現代は、“シミ”や“魔法獣”の脅威も薄れてしまい、ごくたまに起る災害のような扱いですから。原書に選ばれたことを宝くじに当たったような幸運な出来事と考える人もいれば、もっと強大な力を得るための足がかりと考える人もいるでしょうね」
魔法少女になると、世界を守るために戦わなければならないというのがセオリーだけどそういうわけでもないらしい。
「加澄さんの言うように、原書と契約した魔法使いは特別な存在ですから、無事に魔法学園を卒業できれば就職も何も思いのままです。それこそアイドルや芸能人のような仕事だって夢ではありません」
「そ、そんなにすごいことなんだ……」
私が思っていたようなのとはだいぶ違うらしい。
だけど魔法少女かと思ったらアイドルとか芸能人だなんて、現実的なんだかそうじゃないんだか……。
「じゃあ、静ちゃんは? なにか、目標があるの?」
「わたくしは……」
静ちゃんは、いったん言いにくそうに口をつぐむ。
「母のように、なりたくて……」
「お母さん?」
「学園を卒業して立派な原書使いになって、魔法の力で人を助ける仕事がしたいと……」
すると静ちゃんは急に顔を真っ赤にしてうつむいてしまう。
「ど、どうしたの!?」
「だって……恥ずかしいではありませんか……こんな、子供みたいな……」
言われてみれば、確かに静ちゃんの言っているのはまるで「魔法少女」だ。
そっか、だから私は、初めて会った時から静ちゃんのことが――
「静ちゃんの夢、ぜんぜん恥ずかしくなんかないよ! 私、応援する!」
「お忘れかもしれませんが、葉月さんだってなろうと思えばなれるのですよ」
「え……」
思いも寄らない言葉に、私は驚いて目を瞬かせる。
私が? 本物の「魔法少女」になるの?
「葉月さんなら、きっとなれます。わたくしが保証いたしますわ」
そう言うと、目の前のとてもキレイな女の子は優しく微笑む。
静ちゃんと同じ夢を追い掛ける――それはとても素敵なことのように聞こえる。
なりたい。なれるだろうか。
魔法少女に、誰かの夢を守れる人に。
芽吹き始めた夢の蕾はまだ小さく、私の物語はまだ始まったばかりだった。