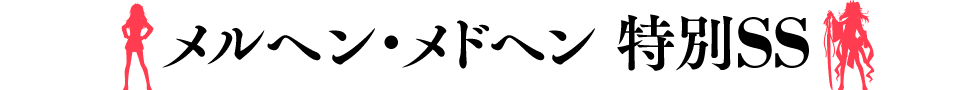『葉月のお友達メモ その1 カザンさんの意外なところ』
私こと鍵村葉月は、この頃ちょっぴり悩んでいた。既視感というか喉のところまで出掛かっているのに上手く言葉にできないというか、そういう居心地の悪さを感じている。
それはいつも“彼女”と顔を合わせる度に思い起こされる。
「あ? なに見てんだ?」
私の視線に気づいたカザンさんがジロリと睨む。
睨むと言ったけど本人にそんなつもりはなくて、単純に視力のせいらしい。暗い場所で本を読んだり書きものをしたりすることが多かったからだとつい先日聞いたばかりだ。
野生って言葉がピッタリの見た目をしたカザンさんには意外な事実だった。
他にもカザンさんには意外な特技というか、なんでも器用にこなすところがある。
たとえば、この間は破れた私の体操着をその場で繕ってくれたし、髪が乱れていたらさっとブラシを取り出して整えてくれたりする。膝をすりむいたらすぐに水で洗ってどこからともなく絆創膏を取り出したりする。
そういう時、私は例の“既視感”をおぼえるのだ。
今日もこうして一緒にお昼を食べている間、ずっとカザンさんのことが気になっていた。
「あ、いや、その、カザンさんって食べ方とかキレイですよね」
「そうか? 普通だと思うが」
「食べ方だけじゃなくって。歩き方とか、座った時の姿勢とか、あと本を読む時の仕草がすごく上品ですよね」
「んだぁ? 急に。褒めたってなんもやらねーぞ」
「い、いえ、そういうわけじゃ……」
「葉月さんは、こう言いたいのですわ。『カザンさんのような粗野粗暴な方が』と」
すると、隣でカレーを食べていた静ちゃんがビシッとスプーンを突きつけて言った。
「ち、違うよ静ちゃん、私は!」
「言ってくれるじゃねぇか静。もしかしてまだこの間のことを根に持ってんのか? アタシにコテンパンにされた時のことをよ」
「コテンパンだなんてお下品な。そもそも、わたくしは負けてはいません」
「だいたい、アタシが昼メシに誘ったのは葉月だぞ。なんで静がついてくんだよ」
「わたくしだって葉月さんをお昼にお誘いしたのです。横入りしたのはカザンさんですわ」
ビシバシと視線でやり合うカザンさんと静ちゃん。あの試合以来、なんだか以前にも増して険悪になった気がするのだが、静ちゃんと付き合いの長い加澄さんに言わせるとむしろその逆らしい。うーん、人間関係とは奥が深い。
「カザンは、子供の頃、すごく厳しい学校に通ってた」
「お、おい、モリー!」
一緒にお昼を食べていたカザンさんと同じ諸国連合のモリーさんがぼそりと答えた。
「こ、子供の頃って? どういうことですか!?」
思いも寄らない新情報に、私は思わず身を乗り出して尋ねる。
「別に、聞いてもおもしろかねーよ」
「そういわずに!」
「わたくしもお聞きしたいですわね。カザンさんがどんな子供だったのか。それはもう活発過ぎて大変だったのでしょう」
私と静ちゃんの「聞きたい」熱視線に負けたのか、カザンさんは溜息をひとつ零す。
「別に、おもしろいことなんかなんもねぇよ。寄宿学校っつーのか、そういうとこに入れられて行儀作法とかいろいろ覚え込まされたってだけだよ」
カザンさんの話を聞くにつれ、そこは寄宿学校でも“フィニッシングスクール”というやつのようだった。
ちなみにフィニッシングスクールっていうのは、いわゆるお嬢様学校で、良家の子女たちが行儀作法や教養なんかを学ぶ場所だ。……ん?
「カザンさんって、いいとこのお嬢様だったんですか!?」
私は思わず声をあげて驚いた。静ちゃんもあまりのことに目を見開いている。
「あー、そういうこともあったってだけの話だ。忘れろ」
カザンさんは面倒くさそうに言うと、それ以上詳しくは教えてくれなかった。
その日、私はいつもより少しばかり上機嫌で図書館の扉をくぐり魔法学園にやってきた。
腕の中には紙袋が一つ。これは練習の後で静ちゃんと二人で食べるのだ。
「むふふ、静ちゃん喜んでくれるかなぁ」
そうやってホクホク顔で歩いていると。
「いただきっす!」
「ああっ!?」
横合いから伸びてきた手が、私の大事な紙袋を奪う。
「そ、それ私のっ!」
「では、さらばっすーっ!」
シャルルさんは目にも止まらぬ速さで逃走する。もはや取り返すことなど不可能だった。あわれ私のおやつは腹ペコ少女たち(シャルルさんとモリーさん)の胃袋におさまるのであろうと、諦めにも似た気持ちで彼女の背中を見送っていると。
「ふんっ!」
「ぐけっ!?」
ちょうど曲がり角に突入しようとしたシャルルさんを容赦のないラリアットが止めた。
「てめぇシャルル……人様のもんに手を出すなってあれほど言ってんだろうが……」
カザンさんだった。
ボキボキ拳を鳴らして、足下に転がったシャルルさんを見おろす。あれは怖い。
「ヒィッ!? あ、姐さん! ちがうんす! こ、これは仕方なくやったことなんす!」
「ああん……?」
カザンさんは「じゃあ、説明してみろ」とばかりに顎をしゃくる。
「えーとっすね、山へ芝刈りに行ったおじいさんが誤ってお昼ご飯のピザをフリスビーのごとく空にぶん投げてしまい、それを見た米軍がついにUFOの襲来かと勘違いして――」
「ウソつけこのバカ!」
「ごるぱすっ!?」
ごちん! とカザンさんのゲンコツが脳天に落っこちて、シャルルさんは珍妙な声を上げて沈黙する。
「悪いな、コイツにはいつも言い聞かせてるんだけど、どうにもちゃんと聞かなくてな」
「そんな、カザンさんが悪いわけじゃ……」
「まぁでも、一応アタシの身内だしな」
カザンさんはそう言うと、今度はうつ伏せに倒れたシャルルさんに向かって、
「おい! いつまで気絶したフリしてんだ! とっとと起きろ」
「あ、バレてたっすか」
ひょこっと起き上がるシャルルさん。さっきもの凄い大きな音がしてたのに、思った以上にタフだ。
「つーか、腹が減ってんならともかくメシは用意してやってるだろうが」
「そ、そうなすけど……なんていうか、たまにはジャンクな食べ物も恋しくなるっていうか……」
「んだぁ? アタシのメシに文句でもあんのか?」
「な、ななな、ないっす! 姐さんの手料理はサイコーっす!」
「あ、あの、ちょっと聞きたいんですがっ!」
「ああ? なんだ?」
私が思わず口をはさむと、カザンさんは面倒くさそうに首をめぐらせる。
「さっき、カザンさんの手料理って言いました? もしかして、シャルルさんたちのご飯って……」
「アタシが作ってるよ。それがどうかしたか?」
カザンさんはなんでもないことのように言う。
「姐さんの料理はなんかやたら手が込んでて繊細っつーか、食べる時もナイフとフォークだし……あ、もちろんめちゃ旨いっすよ!? だけど、量が少なめだし……育ち盛りとしてはもうちょっとこう……あ、すんません。なんでもないっす」
カザンさんにジロリと睨まれて、シャルルさんはまた死んだフリをする。
「ともかく、悪かったな。今度、なにか埋め合わせする。おお、そうだ。なんならうちに来てメシ食っていけよ。大したもんは出せねぇけど、アタシの故郷の料理を食わせてやる」
「は、はい。ぜひぜひ」
そうしてカザンさんはシャルルさんを引きずりながら去って行った。
カザンさんの手料理。ちょっと興味あるかも。
うーん、なんだろこの感じ。
相変わらず私は喉元まで出掛かっている何かが分からず首をひねっている。
カザンさんが誰かに似ていることまでは分かった。だけど、その誰かがわからない。
「よお、葉月。練習は終わりか? これからコイツらと風呂に行くんだけど、オマエも付き合わねぇか?」
「あ、はい! 行きます」
なんてやり取りがあって、私は久しぶりにカザンさんたちと学園の露天風呂に入っていくことにした。
相変わらず露天風呂は老舗旅館のような風情あるたたずまいだった。
最初のうちは「魔法学園なのになんで露天風呂があるの?」とか、疑問を感じていたりもしたけど、学園長さんの趣味なのでいちいち深く考えていても仕方ないという結論に至った。
なにより学校でこんな立派なお風呂に入れるんだからそれでいいじゃないか。
「ヒャハー! でっかい風呂っす!」
私と同じように深く考えないシャルルさんが一番乗りで脱衣所を飛び出した。
「こら、走るなシャルル! 転んだら危ねぇだろ!」
そんなシャルルさんにカザンさんの怒鳴り声が飛ぶ。
「モリーも湯船に浸かんのは身体洗ってからだ!」
今度は湯船に片足を突っ込んでいたモリーさんを止める。
「オマエらいい加減に日本の風呂のマナーを覚えろっつってるだろうが」
「めんどくさい……」
「そっすよ。どーせ誰も見てないっす」
「ダメだ。楽することばっか覚えたらいつか苦労するぞ」
まただ。また既視感だ。
やっぱりカザンさんを見ていると、どうにも懐かしいような気持ちになる。
「葉月、背中流してやろうか?」
私があーでもないこーでもないと考えながら身体を洗っていると、カザンさんがニカッと笑って言ってくる。
「え、だ、だだ、大丈夫です!」
「遠慮すんなって。どーせ、いつもコイツらの背中洗ってやってんだから」
カザンさん相手に遠慮しますはあまり通じない。
今回もまた半ば強引に私の背中を流し始める。
ゴシゴシと、かといって強すぎず弱すぎずなかなか絶妙な洗い方が気持ちいい。
「ったく、コイツらもオマエくらいおとなしくて言うこと聞いてくれりゃ楽なんだがな」
「あはは……」
肯定するわけにもいかず、愛想笑いを浮かべる私。
「失礼な! ぼくはいつも姐さんの言うこと聞いてるじゃないっすか!」
「アタシは最初っからバカなことすんなっつってんだ!」
「カザン……髪、洗って」
「あー、はいはいちょっと待ってろ。ったく、モリーもそろそろ自分で洗えるようになれ」
「善処する」
口ではなんだかんだ言いながらも、カザンさんは世話を焼かずにはいられないようだった。
それに、むしろシャルルさんもモリーさんも、カザンさんに口うるさく言われてまんざらでもないような……?
「あ……ああっ!」
その時、ふいに私の脳裏に閃くものがあった。
「な、なんだどうした急に!?」
モリーさんの頭を洗おうとしていたカザンさんが、私の大声に驚いて振り返る。
「わかった! “お母さん”だ!」
ずっとカザンさんに感じていたこと。カザンさんと、二人の仲間たちの関係。
「カザンさんたちを見ててずーっと何かに似てるって思ってたんです! それって、きっとお母さんと子供たちって感じなんだ! そっか、そういうことなんだ! はー、やっとスッキリしたぁ……」
ずっと引っかかっていたことに答えが見つかって、私はほっとしていた。
ところが、ふと見るとカザンさんががっくりと膝をついていた。
「あ、あれ? カザンさん!? 具合でも悪いんですか!?」
「うぐぐ……」
私が呼びかけても、なにやら苦しげな呻き声が聞こえてくるばかり。
「いやぁ、さすがっす。たったひと言で姐さんを撃沈するとは」
「カザン、どんまい」
「へ……え……?」
わけがわからず困惑する私。なぜかシャルルさんとモリーさんが尊敬の眼差しで見ているような……なんでだろう?