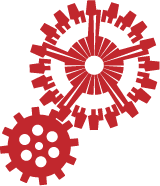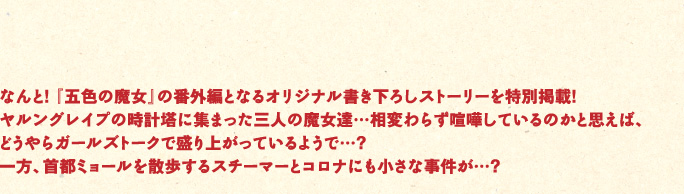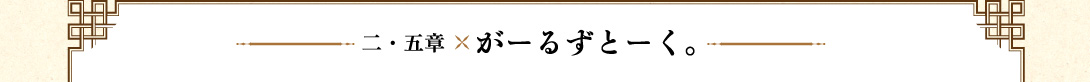天を貫かんばかりの巨大な槍がある。その正体は高さ九十メートルもの建造物だ。
時計塔からは全てが見下ろせる。都市を行き交う人々、煙を挙げて走り抜ける石炭車。汽笛を鳴らす蒸気機関車。
赤みを帯びた煉瓦造りの家屋。
都市を形作る要素は、つら連なって、絡まって、寄り添い合っている。精緻な模様の絨毯にも見える風景。
それらが初夏の日差しに照らされている。
都市の中央に坐する時計塔、それも最上階である第十一階層は最も見晴らしの良い場所だった。
これほどの高さに立つ機会など、普通はない。
人間であろうとソレを超越したものであろうと、眼下の光景に見惚れてしまうものだろう。
ゲルプ黄の魔女も例外ではなかった。
「――」
黒色の大きなトンガリ帽子の奥で金髪が揺れ、金眼がキラキラと輝く。
「へーえ」
彼女は世界を俯瞰する。口端に笑みを浮かべ、つい感嘆の笑みを漏らしていた。
露出の多い黒の衣服の下、心臓が少しだけ早く脈打っていた。
もっと、もっと、しっかりと風景を見てみたい。そんな好奇心に心が支配されていた。
気づけば、ガラス張りの壁に手を伸ばしていた。
黄色の布で丹念に覆われた右手がガラスに触れ、かさついた音を立てる。
この十七歳程度にしか見えない少女、ジャッカルに声が掛けられる。
「あらあら、高い所が好きなの?」
女性らしさと気品を合わせ持つ、つや艶やかな声だった。ジャッカルは窓から離れ、細身の身体を反転。室内に視線を向ける。
時計塔内部であるここ此処には、開けた空間がある。綺麗に掃除の行き届いた木製の壁や床、そして天井は歯車が複雑怪奇に絡み合い、
ガラガラとした幾つもの音を奏でていた。歯車の演奏に熱はない。冷たくて、寂しげで、それでいて一分のズレもない厳格なリズムだった。
室内は閑散としている。調度品も殆どない。古めかしく、頑丈さを誇るかのような円卓だけが置かれていた。
「あぁ?」
ジャッカルは綺麗な顔を忌々しげに歪める。形の良い眉は鋭く立てられていた。先程掛けられた言葉を嫌味と受け取ったらしい。
「人間が多いだけの外を見ていて、楽しいわけがあるか」
すぐ嘘だと分かる台詞を放つや、ジャッカルはガラス張りの壁に背を預ける。それでも壁から離れるつもりはないらしい。
「私達のことなんか気にしないで、好きなだけ外を眺めてたっていいの。貴女、なんだかロマンチックで可愛いわよ?」
再び艶やかな声が飛ぶ。
円卓の席には三人が座っている。しかし声を発したのは、三人の誰でもない。声は円卓の上に置かれた瓶から発されていた。正確には、瓶の中に満たされた青色の液体が言葉を発していた。
ブラオ青の魔女、ラプラス。液体の身体を持つ彼女は、密閉されたガラス瓶の中で楽しそうに踊る。液体がチャプチャプと波打つ。
そんなラプラスのすぐ近くには青年が座っている。彼女の従者であるリーフォンは無表情のまま、まるでそこに自分が存在していないかのように気配を殺していた。
「お姉さんである私としては、そういうの少女的ですごく好きだわ」
ラプラス本人としては、嫌味も悪意もなく言っているつもりである。
「馬鹿にしてんのか、この液体女」
だがジャッカルはそう受け取らなかった。鼻を鳴らして睨みつけてくるばかり。
「別に良いじゃないカ」
円卓に座る人間の一人、白髪を垂らした女が言った。北方の訛りが混じった口調だ。彼女は白蝋の肌を、これまた純白のコートで包み、起伏豊かな身体を席に預けている。
ヴァイス白の魔女、エーメットは美貌をゆが歪めてわら嗤った。彼女は嫌味どころか、まっすぐな悪意を投げつける。
「こう言うじゃないカ? 『馬鹿と煙は高い所が好き』ってナ」
ジャッカルがいきり立つ。
「テメェ! ここから突き落とされてーかっ! 細切れミンチにして豚の餌にするぞ!」
「キャハハハハ」
「ちょっとエーメットもそこまでにしておきなさい。あとジャッカルも下品過ぎるわ」
憤然とするジャッカル。嘲笑ばかりのエーメット。二人に届かない言葉で注意し続けるラプラス。
五色を司る魔女達の会話は、物騒で不穏になるばかりだった。
席には着いている最後の人間。唯一大人しく座っていたセザールは溜息を吐く。この初老の男は、とある事情で〈五色の魔女〉の集会を取り仕切ることになっていた。
「魔女共、頼むから礼儀正しく静かにしてくれないか?」
セザールはとりあえずの要請をした。
この国を仕切る宰相の言葉だ。堅く着込んだ軍服と山のような勲章が威厳を放つ。鉄血の軍人、セザールに逆らう事など誰であろうとあり得ない。その筈だった。だが魔女達にとってはそよ風同然。彼を無視して、言い合いを続けていた。
セザールは額に青筋を浮かべながら、
「席を外す」
それだけを言って、室内を出ようとした。そこでようやくジャッカルはセザールに言葉をかける。それは「場を乱してしまったから謝罪しよう」などと言うしおらしいものではなく、
「あぁ、歳取ると疲れやすくなったりするのか? 悲しいもんだな」
セザールは青筋の数を倍加させて、去るだけだった。
「貴様らと同席しているよりは、一人の方が落ちつくのだ」
セザールは今一度、振り返る。
「……どのみち」
ゲルプ黄、ブラオ青、ヴァイス白――。それぞれを司る三人の魔女を見やり、
「ロート赤が未だ現われない以上、集会は始められんのだ」
室内から去って行くセザール。彼の姿が消えてから、ラプラスが思い出したように言う。
「彼って、あれでも昔は素敵だったのよねぇ」
いずれも百五十年を超える歳月を生きた魔女達。永く生きれば生きる程、未来よりも過去を想うことの方が多くなる。利己主義ばかりの魔女の中で、唯一他人に目をつけるラプラスは懐かしむような口調で言った。
「なんだ、意外と親密だったりしたのカ?」
エーメットの琥珀色の瞳が、興味の視線を向ける。
「あら、そんなんじゃないわよ」
液体にね捻じれる様なうず渦が生まれた。どうやら恥ずかしい思いを表現しているらしい。その様子を見て、ジャッカルは気味悪げに口を曲げる。
「ウネウネしてねぇで話続けろよ。別に興味ないけど」
ラプラスはコホンと一息。
「彼はあれでも一国の英雄よ? 鎧を着込んで、剣を構えて、馬に乗って……。そうやって頑張ってた頃は本当に素敵だったの。青臭くて、この国を良くしようと理想に燃える感じの子だったわ」
円卓にまで戻って来たジャッカルは、自分の席に座る。
「お前って、そういう男が好みのタイプだったりするのか?」
ラプラスは即答する。
「そう。やっぱり若い子がいいわね。夢を追っかけてる感じの子。頑張って頑張って頑張る感じの子」
そこでエーメットが口を挟む。
「ついでに言うト、頑張り過ぎて壊れル。潰れル。絶望すル。そんなやから輩が好みなのだろウ?」
「なにそれ、酷い言い方してくれるじゃない」
ラプラスの力ない抗議に、ジャッカルは肘を立てて呆れていた。
「否定はしないんだな……」
ラプラスは跳ねて瓶内をうごめ蠢く。
「そうね。人生に辛いこと悲しいことはつきものなのよ。そういうのも含めて、人間は好きよ?」
「それってたち性質の悪いサディストなんじゃねぇのか?」
「あらあら、貴女達に比べれば私は優しいわよ」
そこでラプラスは席に座る青年、リーフォンに言葉をかける。
「リーフォンは私のこと、どう思うのかしら?」
リーフォンは深く頷くと、
「はい、主として、素晴らしい方であると思っております」
ラプラスは少し落胆の声音で、
「うーん……、じゅう従ぼく僕としては百点満点の答えなんだけど、つまらないわよねぇ」
「申し訳ありません。必要とあらば千の言葉を以って、ラプラス様を褒め称えますが」
「いえ、結構よ」
液体の魔女は思いついたように、ジャッカルとエーメットの二人に視線を向ける。無論、彼女に眼球はない。
「そういえば、貴方達って全くそういう色恋沙汰を聞かないわ」
ジャッカルは眉をひそめる。
「……そりゃそうだろう。聞かせた覚えはないからな」
「聞きたいわぁ、すごく」
ジャッカルは中指を立てて、
「なんで、私が、教えて、やらなきゃ、ならねーんだ」
一語一語しっかりと強調して言葉を放つ。しかしラプラスは引く様子を見せない。
「私達ってもうちょっと仲良くできるんじゃないかと思うの」
「思わねーな」
「そのためにもね、たくさんお喋りしましょう」
「無視かよ」
「女子しかいないのだから、好きな男の子についての話が王道でしょうね」
「私はそんなことしねーからな」
ジャッカルはだんまりを決め込むつもりでいた。
「あら~、別に私はそれでもいいのよ?」
ここでようやくラプラスはジャッカルに返答する。
「来るかも分からないロート赤を待つ間、私は何時間でも質問攻めできるのだけれど? どうする?」
ラプラスはひたすら喋りかけてくるだろう。「最近はどうかしら?」「魔術研究はどう?」「使い魔は手に入れたの?」「今度遊びに行かない?」「評判のお店があるらしくって」――。想像するだけで面倒だった。これならば三人で取るに足らない話をしていた方が、幾分かマシかもしれない。
ラプラスは、まるでジャッカルの脳内を覗き込んでいるかのように言った。
「さぁ、ジャッカルも会話に参加しましょう」
液体が放つちょっとした圧力。ジャッカルは苦々しい表情を浮かべた。
「この……」
一瞬だけ言葉に詰まる。それからエーメットに視線を投げる。
「……。それじゃあ、エーメットから話せよ」
ジャッカルが返答するまでに奇妙な間が空いた。それもエーメットへと質問を振っている。つまり、ジャッカルは質問から逃げたのだ。それは他の二人の魔女にも分かった。
「そうね。じゃあエーメットから」
しかし彼女達はあえて、ジャッカルに付け入るような真似はしなかった。意地を張るばかりのジャッカルが、動揺を顔に浮かべているのだ。実に珍しいことだった。これは面白くなる、とエーメットとラプラスは確信。エーメットが答えた後、ジャッカルにゆっくりじっくり聞けばいいだけの話なのだ。
「良いだろウ。好みの男のタイプだったナ?」
エーメットは下卑た笑みさえ浮かべて、人差し指を立てた。
「まずは健康な肉体ダ。重量級の筋肉マッチョであるべきダ。優れた肉体は替えガ利かないからナ」
中指を立てる。
「次に良質な頭脳ダ。馬鹿みたいに知能指数が高い奴が良イ。よく考エ、よく生きる人間が良イ」
最後に薬指を立てる。
「最後に忠誠心ダ。私のために誠心誠意、身を粉にして働く奴が良イ。命を捧げるのダ」
エーメットは豊かな胸を張って、
「以下の条件を満たせるものニ、優しくしてやろウ。女でも可ダ」
いかに完璧な美貌を持つエーメットといえど、こうも自信満々に言われては他の魔女もドン引きである。
うーん、とラプラスは唸った。
「貴女、少しは遠慮しなさいよ。いつか後ろから刺されるわ」
「そうもいくまイ。奴隷とはそういうものだろウ?」
ジャッカルは眉間に皺を寄せていた。
「好きな男の話題って言ってただろうが。奴隷の話にすり替えてんじゃねーよ」
エーメットは細い指先で流れる髪を梳いてから、言い放つ。
「次はジャッカル。そうだろウ?」
「はぁ? いや、そもそも私はこんな話は別に……」
ジャッカルはうろたえる顔を露わにするが、ラプラスは嬉々として尋ねる。
「私はジャッカルが一番気になるわぁ」
ジャッカルは口元を手で押さえる。表情を隠そうとしているつもりだったが、眼は右往左往していた。どうにも落ちつきがない。この時、彼女は既に非常に不得手な話題に立ち入ってしまっていたのだ。
「さぁ」「早ク」そう二人の魔女に急かされ、ジャッカルは一層苦い顔になる。
「…………」
ジャッカルは口をもごもごと動かしてから、ようやく言葉を絞り出す。
「恋なんぞ、必要ねーよ」
それはジャッカルにとって精一杯の強がり。
「私は生まれてから、一度もそんなモノを必要としちゃいない」
つまり好きな男どころか、恋すらしたことがないということ。彼女はちょっとした劣等感を覚えながらも、強がる口調で言ってみせた。
「あらまぁ」「おやおヤ」答えを楽しみに待っていた魔女二人。彼女達は一度、顔を見合わせると溜息を漏らす。エーメットですら口をつぐんでいる。
「なんだか行き遅れた年増娘って感じねぇ。いや、むしろ子供すぎるかも」
哀れみさえ滲ませていたラプラスの口調。それがよほど癪に障ったのか、ジャッカルは口をパクパクと開く。
「な、なんだと……」
「出かけてって、男娼でも買ってきなさいよ。銀貨一枚あれば足りるから」
「やかましいわ!」
エーメットの方は失笑を漏らしていた。
「最高峰のネクロマンサー死霊術師とは思えないほド、つまらない返答ダ。もっとこウ、死体に劣情をもよお催すくらいのイレギュラーさが欲しかっタ」
「そんな変態なわけあるか!」
「どうダ? あんまり寂しいようなラ、私のゴーレムを貸し出すガ?」
「いるか! 死ね!」
ジャッカルが思わず立ち上がる。「もう帰る」そう言わんばかりに不機嫌だった。するとエーメットも合わせて立ち上がる。ジャッカルの元まで歩み寄ると、ズイと身を寄せる。
エーメットの背の方が高いため、ジャッカルは彼女を見上げるほかなかった。
「なんだよ……」
エーメットは起伏豊かな体格をしている。ジャッカルからは眼前の二つの丘が非常に邪魔で仕方ない。
「いやいや、恋を知らないのなラ、それはそれで良いんじゃないかと思ってナ?」
エーメットはそっと、ジャッカルの顎に手を当てた。指先の動きでジャッカルの顔を引き寄せる。エーメットも緩やかな動きで顔を寄せる。互いは息が触れ合うほどの距離。体温さえも感じられる。エーメットは薄赤い唇を妖しく踊らせ、そっと耳打ちする。
「私が女を教えてやろウ」
ジャッカルはビクリと小動物のように震えた。耳が真っ赤に染まるや、すぐに顔中が朱に染まる。小さく吐いた吐息はいつもよりも熱くて、そして、
「――んン?」
エーメットの身体が浮いた。彼女の顔面にはジャッカルの頭頂部がめり込んでいた。ミシリと鈍い音が響く。
頭突きである。狙いあやま過たず、打撃はクリーンヒット。エーメットの目がぐるんと反転。鼻血を吹きながらひっくり返った。
そしてジャッカルはほうこう咆哮をあげた。我慢の限界に達したらしい。頭から蒸気を噴きあげんばかりの様子。
「いい加減にしやがれ! このアバズレ共が!」
ジャッカルが喚く。からかい過ぎたのだと魔女達は反省した。ほんの少しだけ。
「……む」
ガス灯が理路整然と立ち並ぶ都市の大通り。石畳の上を行き交う雑踏の中に、一際目立つ影がある。
彼は二メートルをゆうに超えるきょく巨躯だった。羽織ったボロ布で全身を覆い隠し。頭部から鉄製の兜だけが覗いている。それでいて厚みのある身体は、軽く動くだけで周囲の人間を掻き分けてしまう。
彼の進行方向にいた紳士は迷惑そうな顔をして、しかし文句を言う度胸もないのだろう。すごすごと熊の様な巨体を回避していく。
「どうしたの、スチーマー?」
スチーマー蒸気男。その全容は鋼鉄の人形。ジャッカルの使い魔だった。
「ねえってば」
スチーマーの傍ら、といっても足元と変わらない位置に子供がいた。十二歳程度にしか見えない町娘、コロナは年相応の幼い表情でスチーマーを見上げていた。
スチーマーは現在、主であるジャッカルとは別行動を取っている。都市を巡るうちに、偶然に出会ったコロナから勝手に慕われて、一緒に歩いていたのだ。少女がロート赤の魔女だとも知らずに……。
スチーマーは兜から、妙に幼い少年のような声を漏らす。
「いや、なんか向こうの方から怒声が聞こえた気がするというか。おぞましい覇気が……」
知らずと、遥か遠くにそびえ立つ時計塔を眺める。
(五色の魔女ってもう集まってるのかな?)
スチーマーは呑気に魔女の姿恰好を思い浮かべる。彼はジャッカル以外の魔女を見た事がないので、彼女のような姿恰好、性格の人間が五人分揃っているのではと想像する。
「スチーマーッ」
コロナが愛らしい抗議をあげる。細い手を懸命に伸ばして、彼の胴体部を叩く。硬質な金属音だけが響いた。すっかり上の空だったスチーマーは、ようやく我に帰る。コロナは頬を小さく膨らまして。
「無視はよくないよ?」
「うん、ごめん」
スチーマーは素直に謝ると、兜を傾げる。
「それで、なんだっけ?」
コロナは鼻高々に言う。
「スチーマーが行きたいところ、あたしに教えてよ」
「どうして?」
スチーマーとコロナは共に初めて訪れた都市を練り歩いている。
ここまでの道。行動の主導権はコロナが握っていた。少女は都市の観光がしたいとのことだった。徹頭徹尾無邪気な少女は好奇心だけでスチーマーを振り回すばかりだった。
それがここに来て、初めてスチーマーの意志を汲もうなどと言いだした。少女と出会って間もないスチーマーだったが、これには少し驚く。
「優しいんだね」
「えへへ、そうでしょ」
少女は言うと、小さな頭を前に差し出す。燃える様な赤髪とそれを結ぶツインテールが揺れた。
「良い子だから、なでてー」
「了解」
スチーマーは言われるがままにコロナの頭を撫でつける。勿論、鉄製の巨腕がコロナの華奢な身体を傷つけないように注意しながら。
「えへへ~」
彼の大きな掌は、少女の頭をまるまるすっぽり収めてしまった。
コロナは小動物のように喉を鳴らすと、身を震わせた。花の様な笑顔を彼に向ける。御機嫌を取り戻したらしい少女はスチーマーの腕に絡みつく。両手をガッチリ絡めると、頬を擦り寄せた。どうやら、コロナはただ褒めて撫でて貰いたかっただけのようだ。
スチーマーはそんな少女の思惑に気づくことはなかった。それよりも、と考える。
(ボクの行きたいところ、ね)
自らもまた、この都市に初めて来ているのだ。まだまだロクに観光らしいことをしていない自分自身と、主であるジャッカルを思い出す。
「よし、決めたよ」
スチーマーは一つ頷くと、露店の並ぶ一角へと視線を向けた。
「もう一度言うけど、私達は仲良くした方が楽しいに決まってるのよ」
時計塔。ラプラスは波打つ液体の身体を静止させた。円卓に座る二人の魔女を見渡しながら言う。
ジャッカルはまだ顔を赤らめている。イライラと指で円卓を叩いていた。
エーメットは鼻血の出る鼻を抑えながら、仰向けに座っていた。時節、先程のジャッカルのうろたえぶりを思い出して小さく笑う。ジャッカルはその度にイライラと卓上を強く叩く。リズムはどんどん早くなる一方。
ジャッカルとエーメットが、また言い争いを始めるのは火を見るよりも明らかだった。
「この集まりは良い機会になると思うのよね」
「そんなわけあるか」
ジャッカルが即答する。ラプラスはそれを無視しながら、言葉を続ける。
「コロナちゃんもきっとそう言うわ」
「クソガキでクソビッチなアイツがそんなこと言うかよ」
「あらあら酷い物言い。お姉さん、悲しくて泣いちゃいそうだわ」
「液体がどうやって泣くんだよ」
でもね、とラプラスは言う。
「もう心配いらないわ。私がとっておきの物を用意したから」
言うと、ラプラスの背後で終始黙したままでいたリーフォンが自らの胸元に手を差し込む。拳銃かナイフでも取り出されると思ったのか、ジャッカルは警戒して身を引くが、
「何を勘違いしてるの?」
リーフォンが取り出してみせたのは長方形の紙。黄、白、黒、青、赤の五枚からなる色紙だった。彼はそのうち四枚を弾いて飛ばす。紙は卓上をゆるりと滑って彼女達の前に辿り着く。
「絵葉書よ、これは」
黄色の紙がジャッカルの席へ。
白色の紙がエーメットの席へ。
赤色の紙が未だ来ていないコロナの席へ。
青色の紙はラプラスの瓶の上に置かれた。
全員分の紙には、ゆるやかな曲線で描かれた絵が印刷されていた。花びらの模様を現したインクの絵だ。ジャッカルにはゴールドマリー。エーメットにはエーデルワイス。といった具合だ。どれも客観的にみて見事な絵だった。
「どうかしら? 私が頑張って描いたのよ」
液体がどうやって描くのか? そんな疑問を捨て置いて、ジャッカルが興味なさげに絵葉書を振る。
「あー、意味がよく分からないんだが?」
ラプラスはえっへん、と誇らしげに言う。
「文通しましょう。淑女らしく」
ジャッカルとエーメットは自らの手にある色紙を見てから、互いに顔を見合わせる。珍しく意見が合いそうだ、とでも言いたげに三日月の笑みを浮かべ合った。
「嫌だね」
「お断りダ」
二人は同時に色紙を握り潰した。
ラプラスはブクブクと気泡を吹きだした。
「貴方達って本当に可愛くないわ……」
立ち並ぶ露店の一つに入ったスチーマー達。普通に立っていれば天井に頭が当たるため、背を丸めて店先に入った彼は、布張りの店の奥で目当ての物を見つける。
「へー、そんなのが欲しいの?」
一緒についてきたコロナが彼の手中を覗き込む。
「うん、まあね」
スチーマーが店番である老婆に商品を出すと、老婆は眼を剥いた。スチーマーの異様な巨躯に腰を抜かしそうになっているのだ。
「…………ま、まいどあり」
それでも、なんとか対応してくれた。彼は銅貨を一枚支払うと、ソレを持って店を出る。
コロナはスチーマーの隣を跳ねて回る。
「なんでなんで? もっと色んな物があったよね?」
彼等が立ちよった店は雑貨屋だった。様々な瓶類や使い古しの衣服、インクやランプといった統一性のない物品ばかりが並んでいる。近場にある質屋から流れてきたものを此処で売りさばいているらしい。 「別にボクが欲しかったわけじゃないんだ」
スチーマーの手には色違いの色紙が五枚あった。それらは時計塔に座って並ぶ魔女達を想起させるもので、
「僕の友達が知人と会うらしくってね。手紙で文通でもしてくれれば、仲良くなれるんじゃないかと思ったんだよ」
子供のような優しげな想いだった。スチーマーは黄色の紙を掲げると、偏屈な一人の魔女を思い浮かべる。
使い魔であるスチーマー。その正体に薄々気づいているコロナは、何を思ったのか? それは魔女らしいものであったに違いなく、
「へー……」
一瞬だった。コロナの瞳が揺れ、嘲りの色が浮かぶ。しかし少女はすぐに満面の笑みを取り繕う。眼を爛々と輝かせ、手を広げた。
「すっごく素敵だと思う!」
スチーマーは頷くと、小さく漏らした。
「うん、ジャッカルも喜んでくれるといいなぁ」