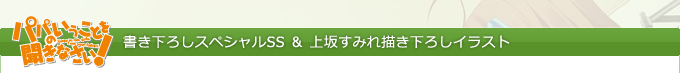
 『五月五日の小鳥遊家』
池袋のはずれに位置する、鬼子母神や東京音楽大学がほど近い、閑静な住宅街。そこに小鳥遊空たちが暮らす、小さな庭のある大きめの一軒家がある。 空、美羽、ひなの三人は、思い思いにGW最後の日を過ごしていた。 「おいたん、まだかなー」 朝食を終えてリビングでくつろぐ三女のひなが、毎日恒例になっている質問をした。 四歳児にしては長い髪を揺らしながら、彼女のナイトである老犬ジュウベエと犬用のオモチャで遊んでいる。 「明日には帰ってくるよ。きっと、ひなにいーっぱいお土産買ってきてくれるんじゃない? ね、美羽」 笑顔でそう言ったのは、しっかり者の長女、空だ。 キッチンの方をちらちらと気にしながら、リビングのテーブルを拭いている。 「ふふっ、そうだね。お姉ちゃん。あー、いいなぁ、叔父さん。避暑地でGWを過ごすなんて。あたしも行きたかったな」 けだるげに雑誌をめくっていたアイドル張りの美少女、次女の美羽はため息をつく。その仕草もとても可愛くて、空は思わず笑顔になってしまう。 「でも、佐古さんは一緒に行こうって言ってたじゃない。用事があったのは私たちの方なんだから」 「そうなんだけど。やっぱりこれでGWが終わりだと思うと、ちょっと寂しいんだもん」 ツインテールの美少女が唇を尖らせた瞬間、明るい声が響いた。 「じゃあ、オデカケしまショ! 休日ですモノ! 私もミウたちと遊びに行きたいワ!」 エプロンで手を拭きながら、満面の笑みを浮かべているのは……サーシャだった。 豪華な白金髪とメリハリの利いたプロポーションを持つこの女性は、美羽の実の母だ。今年の一月に再会したばかりであり、三姉妹のことをいつも気にかけてくれている。 現在はロシアでデザイナーとして身を立てているが、大きな仕事が片付いたということで四月の終わりから来日していた。 「だけど……昨日もお買い物につれていってもらいましたし、悪いです。ただでさえ、せっかくのお休みに、私たちの為に留守番と家事ばかりしてもらってるのに」 すまなそうに空はサーシャの顔を見た。サーシャは大げさな身振りで反論する。 「ソラ、そういうこと言わないデ。せっかくGWはユウタに任せてもらったんダカラ、ワタシがアナタタチを独占できるチャンスなのヨ 微かに異国のなまりが残る言葉で長女を優しく諭すと、次女と三女に向き直る。 「サア、どこでもいってネ。といっても、明日にはユウタが帰ってくるから、今日ダケネ」 今年は都合良く6日が日曜日で長めのGWとなっている。ロ研とテニスサークルの合同で避暑地に出向いた祐太は、たっぷり羽を伸ばしているはずだ。 「ひな、どこか行きたいところある?」 アイドルばりの美貌と繊細な気遣いを併せ持つ美羽が、天使のような容姿をもつ小鳥遊家の末姫に笑顔を向けた。ただ、母の質問に直接答えるのを避けたようにも見えて、空は微かな不安を感じたのも事実だった。複雑な事情から離ればなれになったこの親子には、いくつかの出来事を経て判りあえた今でも、微妙な距離がわだかまっているのだ。 「んー、でも、ゆうえんちもでぱーともいったよ……。どうぶつえん?」 「GWの動物園なんて……ひなも遊園地で懲りたんじゃない?」 「うー、そうだったお……」 ひなと美羽は、GWに入って出かけた近くの遊園地の惨状を思い出してげんなりしている。はしゃいで出かけた四歳のひなは、遊具の待ち時間に疲れ果て、更にフードコートでも座ることが出来ず立ち食いするハメになって半泣きだったのだ。三姉妹とサーシャは、遊園地で酷い目にあったことを祐太に話さないでおこう、と約束したくらいだ。サーシャは苦笑いし、空もため息をついて頷いた。 「観光地は……現実的じゃないよね。デパートも混んでるかなぁ」 「池袋自体は、普段より空いてる感じなのにね。上野動物園は……きっと地獄だよ」 「ひな……どうぶつえん、がまんする……」 アイデアが潰れてしょんぼりしているひなの足もとで忠犬がぱたと尻尾を振った。 「わふ」 控えめに鳴くのは、小鳥遊家のペット、老犬ジュウベエだった。数奇な縁で小鳥遊家にやってきたこの犬は、ひなの笑顔にいつも貢献している大切な家族だ。 「じゅーべー……。そーだ、ひな、じゅーべーがいっしょにいけるところがいい!」 「ふふっ、いいアイデアだね。温かくなってきたし、近所の公園でお弁当食べようか」 空が微笑むと、美羽とサーシャも笑顔を返す。そして早速、お弁当作りが始まったのだった。 程なく、池袋の外れに位置する住宅街を歩く四人の姿があった。人目を引く容姿を持つ家族は道行く人達の視線を集めているが、本人達にはまったく自覚はない。 「そらねーたん! ほらほら、あれ!」 「え……? あ、鯉のぼりだね」 ひなが嬉しそうに指さしたのは、住宅地のところどころに翻る五月の風物詩だった。 「コイノボリ……って、ナニ? 見たコトはあるんだけド、忘れちゃったワ 北欧育ちのサーシャさんが、ひなを挟んで歩く美羽に尋ねる。 「男の子がいる家で、五月五日に飾る日本のイベントだよ。三月三日が女の子の節句。五月五日が男の子の節句なの。記念日のお祭りみたいなものかな 美羽が説明する隣で、ひながぷーっと、ふくれている。 「おとこのこだけずるいおー! ひなも、こいのぼりほしい!」 「ふふっ、ひなはひな祭りで大きなひな人形飾って貰ったじゃない 「でも、こいのぼりかっこいいお!」 目をキラキラさせるひなに、年長者たちは微笑んでしまう。 「アラ、ひなはカッコイイがスキ? カワイイがスキかとおもったワ」 イタズラっぽく訊ねるサーシャに、ひなは大きな目をくりくり動かす。 「どっちもすき! ひな、りょうほうがいい!」 「さすが、女の子はそうでないとね!」 美羽が明るく笑う。そしてひなの手をひいて歩き出す。 「きっと公園に大きいのがあるよ。そこでお弁当食べて、ひなが独り占めしちゃお!」 「うん! いこ、じゅーべー!」 「わふ」 元気に走り出す年少組を目で追って、空とサーシャは胸の温かさを感じていた。 「フタリとも、ころんじゃダメヨー」 ゆっくりと追いかけるサーシャと空は、並んで語り出す。空にとっても、サーシャはものごころついた頃から小学校に入る直前まで一緒に暮らした母のような存在なのだ。 「サーシャさん、サーシャさんの国にも、鯉のぼりみたいなもの、あるんですか?」 「ンー、オイワイってコト? いっぱいあるワヨ」 サーシャはニコニコと笑顔になる。 「もともとワタシがいた国はロシアの影響が強かったカラ、ロシアのお祭りにニテルわネ。というか、ワタシの生まれた頃はまだ共産党政権だったシ……」 全然ピンとこない話に、空はきょとんとしてしまう。 「お祭りって、政治と関係あるんですか?」 「フフッ、ニホンだとピンとこないワヨネ。デモ、そういうモノなのヨ。五月だと……春と労働の日ネ。とっても大きなパレードがあるのヨ」 「へえ……素敵ですね」 「ムカシはニホンでも盛んだったのよ。ニホンではメーデーっていうんだけどネ」 サーシャはさらりと言って、遠い目になる。 「ワタシがニホンを離れた内戦のアト……ワタシはワタシのママとロシアに移り住んだケド……生まれたクニにいたら、別のお祭りがあったんダト思うワ。ワタシは、十代のハジメからニホンに来てたから……生まれたクニのお祭りは、あまり知らないノ」 過ごしてきた歴史を振り返るような、いつもと違う笑顔に空はどきっとする。サーシャが、凄まじい美人だと気付いてしまう瞬間だった。そんな空の様子に気付いたのか、サーシャはぺろっ、と舌を出す。 「アラ、ごめんネ、ソラ。こういうの『トシヨリノクリゴト』っていうのヨネ」 何事もなかったように笑顔に戻ったサーシャは、空の手を掴んだ。 「ロシアの一番大きなお祭りはネ、クリスマスよ。新年のお祝いから、1月7日のクリスマスまで、ずーっとお祝いするんダカラ! ソラたちも、今度一緒にお祝いしたいワ!」 「ええっ、クリスマスって、12月25日じゃないんですか!?」 「ソーナノ! 不思議ヨネ! でも、ニホンでクリスマスしてからロシアに帰ったラ、二回もクリスマスが出来てオトクよネ!」 人に気を遣う時の美羽にそっくりの表情で、サーシャは笑う。空は彼女の笑顔を見ながら、本当に美羽のお母さんなんだな、と思うのだ。空は、微かな胸の痛みを感じていた。 その正体がなんだか、空自身にも判っていなかったけど。空がその事を考える前に、明るい声が耳朶を打つ。 「そらねーたん! さーしゃ!」 「もー、おねーちゃん、ママ、なにしてるのーっ!」 少し離れたところで、話し込んでしまった二人に気付いた美羽とひなが手を振っている。 「……行きましょうか、サーシャさん」 「そうネ」 そういって、サーシャは町並みの所々で翻る鯉のぼりを背景に満面の笑顔を見せるふたりを、まぶしそうに目を細めて見つめる。 「ね、ソラ。ワタシには、今がマイニチ、パーティみたいなのヨ。ソラがいて、ミウがいて、ヒナがいて……ミウのいうとおり、今日も……キネンビね そんなサーシャの手を空は握り返した。 「これからいっぱい記念日が出来ますよ、サーシャさんと美羽に。いつか……私たちもロシアに連れて行ってくださいね」 「モチロン! その時は、ユウタもイッショにネ!」 そういうと、サーシャは空の手を引いて走り出す。 「き、きゃあっ! さ、サーシャさんっ!?」 「ゴメナンナサイ! じゃあ、コイノボリの下までキョウソウしまショ!」 「えーっ、ママ、いきなりっ!?」 「ひな、まけないおーっ!」 あっという間に二人を追い越したサーシャと空を、美羽とひなが追いかける。四人は、くっつきあって走り出す。 祐太が帰ってくるまでの、束の間の四人暮らしは、こんな風に過ぎていく。 この後に待っている波瀾万丈な物語に、まだ空は気付いていない。 ただ、こんな優しい日常が妹たちに帰って来たことを素直に喜んでいた。 心の奥で、大切な叔父がこの場にいないことを、寂しく思いながら。 こうして、空達の五月五日は笑顔の中で過ぎて行ったのだった。 <了> |