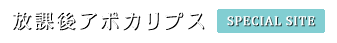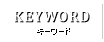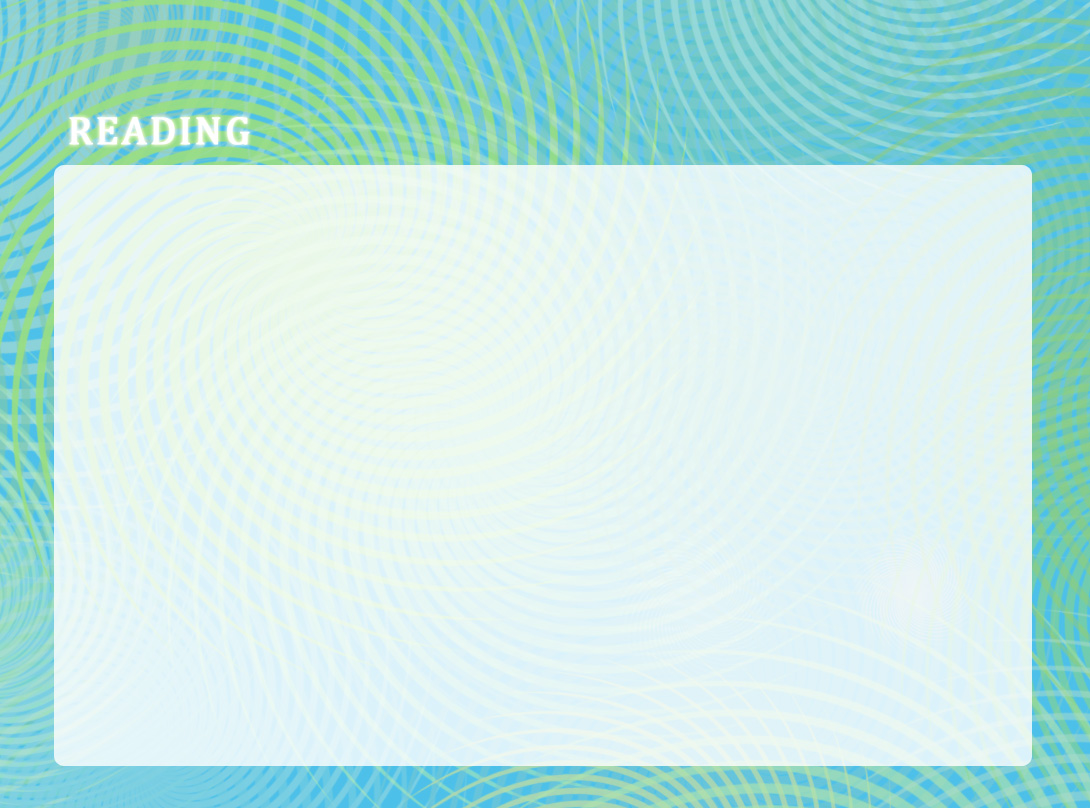
保健室登校、という言葉があるらしいけれど、僕の場合は司令室登校だった。
もちろん、クラスメイトにノートを写させてもらうなり移動先を訊くなりすればいいだけの話だ。そもそも人に自分から話しかけることが苦手だった僕は、病気をしていなくてもいずれなにかしらの些細なきっかけで孤立していたのだろう。
とどめになったのは生物の時間だった。実験授業にはじめて出席したら、六人ずつの実験班がすでにできあがっていて、僕はどこの席に座ったらいいのかもわからなかった。
「ああ、藍沢は休んでたんだっけか?」と先生はのんびり言った。「それじゃあ、どこかの班にてきとうに混ぜてもらえ」
クラス全員が迷惑そうな顔を僕に向けてきた気がした。僕はトイレにいくと偽って生物室を出ると、そのまま戻らなかった。
それ以来、登校してもクラスに顔を出すのが気詰まりで、かといって不登校になってしまうほどの勇気も持てず、僕は図書室や裏庭で時間を潰すようになった。
陽当たりの悪い湿った土の上で、遠くチャイムを聴きながら弁当をもくもくと食べていると、中学のときとなにも変わっていないな、と情けなくなってくる。とくにいじめられていたわけでも無視されていたわけでもないけれど、どうしてもクラスになじめなかった。同級生たちが無言で僕を詰っているように思えてしかたなかった。なんでおまえはここにいるんだ、と。だから休み時間はトイレの個室にこもって本を読んだり音楽を聴いたりして過ごした。司書の先生がいないときには一日中図書室で時間を潰した。
高校でなにもかも心機一転やり直そうと、僕の中学からはまずだれも進学しなそうな東京の高校を無理して受けてやっとの思いで合格したというのに、けっきょく同じ繰り返しだ。考えてみれば当たり前だった。僕自身が変わっていないのに、僕を取り巻く世界がそう簡単に変わるわけはないのだ。
人生はゲームじゃない。ボタン操作ひとつでリセットはできない。これが、僕の生きてきた十五年間で学んだいちばん大切なことだ。
でも僕は間違っていた。人生は実にそのままの意味でゲームだった。
最悪なことに、リセットできない点に変わりはなかったけれど。
最初は彼女の存在に気づかなかった。剥き出しのコンクリートを踏む新鮮な感覚を味わい、手すりに近寄っていつもよりずっと広く見える空をぐるりと見渡し、眼下の校庭から聞こえてくるホイッスルと砂っぽい足音のリズムを聞くともなしに聞き、手すりに背を向けて寄りかかって大きく息をついたところでようやく気づいた。
階段室の屋根の上に、人影があった。僕はびっくりして後ずさった。女の子だ。うちの制服を着ているからにはうちの生徒なのだろうけれど、その目つきはなんだか高校生とは思えないくらい大人びていた。いや、大人びていたというのは正確な表現じゃない。もっと深くて厳しい、一切の生物の存在をゆるさない塩湖みたいに澄んだ眼だった。
だからだろう、僕はしばらく魅入られてしまった。
彼女はだいぶ前から僕に気づいてたらしく、身を低くして警戒の色もあらわにこちらをにらみ下ろしていた。長いすべらかな黒髪を無骨なまでに大きなヘッドフォンでおさえつけているせいで、人を寄せつけない雰囲気はいっそう際立っていた。
「……あ、ああ、ごめんなさい」
ようやく我に返った僕は言った。
「その、人がいると思ってなくて」
すぐに校舎内に戻るべきだったのだろうけれど、そのためには彼女の見ているすぐ真下を通過しなければならず、気詰まりで手すりを離れられなかった。
彼女はむっとした顔で階段室の屋根から飛び降りた。黒髪とスカートが春風にひるがえって大きく広がる。僕が気圧されて言葉を失っている間に、彼女はさっさと校舎に入っていってしまった。
扉がつっけんどんに閉められた後で、僕は大げさに息をつく。視線が合っている間まわりの音が聞こえなくなるくらいの強い瞳だった。
だれだろう、あれは。こんな時間に屋上にいたということは、僕と同じく授業をさぼっていたということだろうか。
ともかくこっちの校舎の屋上を使うのはやめよう、と僕はドアをくぐった。
でも彼女とは翌日すぐに再会することになった。南校舎の方の屋上なら大丈夫だろうと思って二時限目の終わりに行ってみたら、やはり階段室の上に黒い影がうずくまっていたのだ。膝を抱えてしゃがんでいた彼女は、身を乗り出してきて僕を見る。ヘッドフォンに挟まれた不機嫌そうな顔がむっとしかめられる。
「あ、あのっ、……ごめん」
僕はあわてて言った。
「こっちならいないかと思って、その」
彼女がまたも屋根から下りようとしたので僕は両手をばたばた振って制止した。
「い、いや、いいよ、僕がいなくなるから、ほんとごめん」
首が痛くなるくらい顔を伏せたままドアに飛び込んだ。少しでも視線を上げたら彼女の太ももとかスカートの中身が目に入ってしまいそうだったからだ。一階まで足を止めずに駆け下り、階段の裏側の埃っぽい空間に身を押し込んでようやく一息ついた。
屋上は彼女のテリトリーなのか。しかたない、あきらめよう。
三度目の遭遇も信じがたいことにその翌日だった。司書がいなかったので図書室で一日過ごそうと決め、最近お気に入りの怪奇小説のシリーズを読み進めようと棚を探したら、読み途中の三巻だけがなかった。しかたない、飛ばして読むか、と四巻を抜き取り、他にも何冊か選んで重ねて抱え、机の並ぶスペースに行ったら見憶えのある人物が座っていた。彼女だった。
あちらも驚いていたが僕の驚きはそれ以上だった。三日連続で顔を合わせたのもそうだが、彼女が読んでいたのがまさに僕が探していた三巻だったからだ。僕は口をぱくぱくさせて、自分の手の中の一冊と彼女の手元の一冊を何度も見比べる。彼女も気づき、むうっと唇をすぼめ、立ち上がった。
「この栞、ひょっとしてあなたの?」
はじめて聞く彼女の声だった。しばらく、それが僕に対する質問だということを理解できなかった。彼女がページの間から引っぱり出した細長い和紙片は、たしかに僕がついこないだ挟んでおいたものだ。
「……う、うん」と僕はうなずく。
「じゃあ早く読んじゃって」
彼女は本を僕の方に押しやってくる。
「いや、いいよ、先に読んでも」
というか僕は出ていくよ、と言いかけた僕を無視して彼女は本棚に向かった。僕は途方に暮れてしまう。このまま彼女の厚意――といっていいのかわからないが――に甘えてこの三巻を今ここで読むのもなんだか気が引けるし、かといってさっさと出ていくのも気持ちを踏みにじるみたいで失礼だし……。
ちらと彼女の様子をうかがう。そこで僕ははじめて、彼女がブレザーの左腕に巻いている赤い布帯に気づく。腕章だ。白抜きで『1C 学級委員』とプリントされている。学級委員なのか。ていうか授業しょっちゅうさぼってるくせに、どうして学級委員の腕章なんてちゃんと着けてるんだ?
と、そんな疑問がどうでもよくなるくらい重大なことに気づいた。さっきから彼女は本棚の同じ箇所を何度も何度も指でたどって探しているのだ。まさか、と思いつつも、僕は思いきって声をかけた。
「あの」
ヘッドフォンをしているから聞こえないかな、と心配したけれど、彼女はこっちを見た。
「ひょっとして、探してるの、これ?」
さっき一緒に持ってきた恋愛小説シリーズの二巻を持ち上げてみせる。自分でも読んでおいてなんだが、こんなべたべたに甘いのも読むのか、と意外に思った。彼女は目を見開き、頬を染めて横を向く。
「ち、ちがっ、そ、そんな恥ずかしいの読まない。だいたい主人公が鈍くていらいらするやつは大嫌い」
「読んでんじゃん」
思わず口に出してしまった。彼女は真っ赤になって、大股で図書室を出ていった。
僕は椅子に腰を下ろして頭を抱え、盛大に後悔した。怒らせてしまった……。たまに勇気を出して人に話しかけてみればこれだ。もう僕なんて一生無言でいた方がいいのかもしれない。いや、でも、今のって僕がなにか悪いのか?
まあいいや。とにかく結果的に図書室でひとりになれたんだ。続きを読むか。
ページをめくってはみるものの、彼女のことが気になって小説の内容なんてちっとも頭に入ってこなかった。あいつはなんなんだろう。僕と同じようにクラスになじめなくて授業にも出ずにひとりで時間を潰しているかわいそうなやつだろうか。あのつんけんした態度なら孤立するのも無理はない、自業自得だ。……と考えたところで、全部自分にも当てはまるので落ち込んできた。
1Cと腕章に書いてあったっけ。一年C組なら隣のクラスか。でもお互いにほとんど教室に顔を出していないとなれば見憶えがないのも当然だった。
それ以上彼女について考えていてもしかたがないので、僕はむりやり小説に意識を戻そうとする。でもなにかがまだ引っかかっている。一年C組。……C組?
たしかこの高校は一学年が二クラスずつじゃなかったか。C組なんてあったか?
ぎょっとした。教室は空っぽだった。
……いや、教壇の前にひとつだけ、机と椅子がぽつんと置かれている。
それだけだ。教卓もないし、掃除用具入れにはなにも入っていないし、黒板消しもチョークも見当たらないし、掲示板はまっさらだ。
おそるおそる足を踏み入れる。早朝の静けさがしんと肌に染みいってくる。
あらためて見回す。ほんとうに、机ひとつを除いてなにもない。壁際の床には埃がたっぷりたまっている。日焼けして変色したカーテンが束ねられもせずだらりとレールからぶら下がっている。黒板の粉受けはきれいなままだ。
なんだこの教室……。
机に近づいてみる。深緑色のファイルが一冊、のっている。出席簿だ、と気づく。
取り上げてめくってみると、四十いくつに行分けされたリストのいちばん上の欄にぽつんと一人分の名前だけが記されていた。
『七連坂 未咲』
しちれんざか・みさき。
これがあの女の子の名前なんだろうか。一人だけしか載っていない出席簿っていったいどういうことだ。
くだらない妄想が次々に湧き起こってくる。あいつ、ひょっとして幽霊じゃないか。ずっと昔、在籍数が多くて一年C組が存在した頃の生徒で、自殺かなんかで地縛霊になって学校をずっとうろついている、とか。あるいはもう少し現実的に、ひとりぼっちをこじらせすぎて、空き教室を使って自分だけのクラスを捏造した、とか――
背後で戸が開く音がして、僕は驚いて振り向いた。
戸口のところに彼女が立っていた。口を半開きにして僕を見つめ、それから首にかけていたヘッドフォンを急いで耳に着ける。
「なっ、なんでこんなところにいるの!」
視線をそらし、ぶっきらぼうな声で彼女は言った。
「あっ、ご、ごめん、勝手に入って」
憤然と歩み寄ってきた彼女は、僕の手から出席簿を引ったくると、『七連坂未咲』の名前の横、今日の日付の欄に丸印を書き込んだ。それから机に鞄を下ろす。
やっぱりこいつが七連坂未咲なのか。
「……あのう、ここって……空き教室、だよね?」
そうっと訊いてみた。七連坂未咲は首を振った。
「教室じゃない」
「……え?」
「ここは司令室」
ぽかんとした間があった。
言われたことが理解できなかった。シレイシツ、というその単語が頭の中でしかるべき漢字に変換されるのにかなりの時間を要した。
「……司令室? えっと、どういうこと?」
「わからないならいい」
七連坂未咲は首を振り、出席簿を持ったまま教室の戸口に向かおうとした。
いけない、昨日怒らせてしまったことをせめて一言でも謝らなければ、と僕は思い、どう言葉にすればいいのかも深く考えずに呼び止めていた。
「あ、あの、ちょっと待って」
未咲は足を止めて振り返った。露骨に不機嫌そうなので僕はたじろぐ。
「なに?」
訊かれ、答えに窮し、なんでもいいから言わなければと焦って口を開き、出てきたのはこんな言葉だった。
「……あのシリーズ、二巻からは主人公がちょっと鈍くなくなってるよ」
なに言ってんの僕? 謝るんじゃなかったのかよ?
しかし発した言葉を引っ込めることはできない。未咲は一瞬面食らった表情になり、それからぷいと横を向く。
「だからなんなの。あ、あんな甘ったるいの、読むわけない」
わざとらしいくらい足音を大きく響かせて未咲は廊下に出ていった。僕は様々な後悔にまみれて床にしゃがみ込んだ。
しかしその日の三時限目、図書室に行ってみたら、例の恋愛小説のシリーズは最終巻までごっそり貸し出し中になっていたので、ちょっと笑ってしまった。
水曜日は、校舎裏に積まれた廃棄予定の古い机に腰掛け、ぼんやり音楽を聴いて過ごすことにしていた。ちょうど曲の切れ目にチャイムの音が重なり、イヤフォンを外して時刻を見る。六時限目が終わるところだった。
さて家に帰るか、と机の山の上から降りようとしたときだった。
「あーっ、いた! 藍沢!」
やかましい女の声が耳に突き刺さり、僕は転げ落ちかけた。重なった机が軋んだ。校舎の角から姿を現し、こっちを指さして近づいてくるのは、髪を茶色く染めて制服の大胆に着崩した女子生徒だった。
「ほんッと捜したんだからね! サボるなら同じ場所でサボれっての、いつどこにいるかもわかんないんだから!」
「え、あ、あの?」
捜した? 僕を? ていうか――だれ?
「信じらんない!」とその女子生徒は目を見張る。「同じクラスなのに憶えてないの? あんたも三回か四回は授業出てるでしょぉ? あたし有間、後ろの席の! 有間くるみ!」
三回か四回で同級生の顔と名前が一致するようなまともな人間なら、今ごろ僕はこんな場所でサボってたりしない。
「ほんっとに憶えてないの? こんな可愛くて読モまでやってて最近マスカラも思い切ってパール入りに変えちゃったくるみさんを憶えてないの?」
「初対面のときにその痛い自己紹介やってくれてたら憶えてると思うけど」
「なんだと」と彼女は僕の襟首をねじり上げた。細腕に見合わず怪力だった。「痛いんじゃないの、こういうキャラ作りがティーン誌では受けるの!」
「ごめん、ごめんってば!」
僕、どうやら胸の内にしまっておけばいいことをぽろっと漏らす癖があるらしかった。未咲にもそれで怒られたし、人と喋っていないとこういう悪癖も治らないまま成長しちゃうのか、と暗い気持ちになる。
「って、こんなことしてる場合じゃなかった。早く来て、この後ホームルームなんだから! 今まで学級委員がいなくて全然なんにも話が進まなかったんだからね!」
「……学級委員?」
有間くるみは、答えるよりも早く僕の左腕をつかむと、なにか赤いものを取り出して巻きつけてきた。
「な、なにっ?」
「暴れるなっての、安全ピン刺さるよ!」
腕章だった。『1B 学級委員』という文字が白く染め抜いてある。未咲がつけていたものと同じだ。
「……なんで僕が学級委員なの?」
「委員決めるときに休んでたでしょ。だからみんなやりたがらなくて押しつけたの」
僕は天を仰いだ。横暴にもほどがある。くるみは僕の手首をつかんでずんずん歩き出した。僕は足下に置いてあった鞄をあわてて取り上げると、彼女の手の感触にどぎまぎしながらもついていく。引っぱらなくても歩ける、という言葉さえ口にする勇気が持てない。二階の1B教室にたどり着くまでの間、すれちがう他の生徒たちの視線が痛かった。
「藍沢見つけた、連れてきたよ!」
くるみは教室の戸を開けてそう言うと、僕を中に引きずり込んだ。たちまち視線が集まり、僕の身はすくみあがる。まばらな机と、十数人の男女たち。僕を見る目は不審と不安と猜疑と好奇が四分の一ずつだった。僕の被害妄想かもしれないけれど。目を伏せると、視界の端、教壇の隅で担任教師がパイプ椅子に座って苦笑しているのが見えた。まだ赴任してきたばかりの若い女の先生だ。僕が授業に出ていないのを知っていてもなにも言ってこない内気そうな人だから、この場でもたぶんなんの助けにもなってくれないだろうな、と思う。
「……藍沢?」「へえ、学校には来てたんだ」「何度か見たよトイレとかで」
クラスメイトたちが交わす言葉の端々が聞こえてきて、僕は真剣に逃げ出すことを検討し始める。でもくるみが僕の背中をずいずいと押して教壇の向こう側に立たせる。
「生徒会に怒られちゃったんだから、うちのクラスだけ学級委員が全然働いてなくて決めるものも決めてないって! 今日のホームルームはあんたがちゃんと仕切ってよ!」
「い、いや」
僕は言い返そうとして咳き込む。みんなから注がれる視線に憐れみが混じり出す。
「仕切れって言われても、なにやればいいのか」
「いいから早く始めろよ学級委員」「俺さっさと済ませて部活行きたいんだよ」「あたしも」
野次が飛び、僕はまたも顔を伏せてしまいそうになる。
「でも、あの」からからの声をなんとか押し出す。「まだクラス全員集まってないみたいだから、その」
なんとか時間を稼ぎたい一心で言った。でも、教卓のすぐ近くの席のくるみも、教壇の脇の先生も、そしてクラスメイトたちも、怪訝そうな顔になる。
「そろってるよ」とだれかが言った。
「サボってたのはおまえだけだよ」とべつのだれかが言い、笑い声がいくつもあがる。
僕は身をすくませながらも教室を見回す。だって、どう見ても十何人しか――
そこで気づく。
机が足りている。
くるみの前の空席は、彼女の話からして僕の席だろう。そのひとつを除いて、すべての椅子に生徒が着席している。全員、そろっている……? 目で生徒を数える。十六人だ。
「うちは十六人学級だよ」「授業出てないからって、だいたいの人数くらいわかるでしょ」
「そ、そうなんだ」
僕は出てもいない額の汗を拭うふりをした。十六人学級? そんなに少なかったか? おかしい。憶えている限りでは、普通に四十人弱はいたはずだ。いくら僕が入学直後からほとんどクラスに顔を出していないといっても、倍以上も数を勘違いするものだろうか。
「だから早く始めろってば」
「もーっ、しゃあないから手伝うよ」とくるみがげんなり顔で立ち上がった。「あたしが黒板書くから、藍沢はほら、そこ、議題がファイルにまとめてあるよ」
「あ、う、うん」
「くるみが最初から学級委員やればよかったんじゃないの」
女子生徒のだれかが冷やかした。
「やだよ! 中学でずっと出席番号1番で、色々雑用押しつけられてきたんだから」とくるみは口を尖らせる。「せっかく藍沢がいるんだから全部押しつけるの!」
出席番号1番だから僕は学級委員にさせられたのか、と絶望的な気分になる。それじゃあ委員決めの日にたとえ出席していたとしても、どうせこうなる運命だったってことか。
しかたない。
教卓の上に置いてある『1B』というラベルの貼られた水色のファイルに目をやる。なにをどうすればいいのかはよくわからないけれど、とにかくこの場をなんとか切り抜けてさっさと帰ろう、そして明日から完全に不登校になるべきか検討しよう――と、ファイルをつかみ上げた、その瞬間だった。
チャイムが鳴るのが聞こえた。
メロディこそ同じだけれど、ひどく不愉快に割れた響きだった。しかも、一打ちごとに音が大きくなってきている。僕はなにごとかとスピーカーを見やる。クラスメイトたちも表情をこわばらせてあたりを見回している。頭痛がしてきた。頭蓋骨をハンマーで直接叩かれているみたいだ。両手で耳をふさいでも音量は堪えがたいほどになり、僕は歯を食いしばって教卓に突っ伏した。なんだこれ? なにが起きてるんだ?
チャイムが止んだ。
僕は顔を上げる。
骨の内側でまだ痛みが反響していて、頭がくらくらしていた。目もいくぶんかすんでいて、あたりが薄暗く見える。……いや、ほんとうに薄暗いのか。窓ガラスの向こうの空がどんより灰色に塗りつぶされている。さっきまで晴れていたはずなのに。
クラスメイトたちはみんな椅子からずり落ちたのか机の間の床に倒れていた。かすかなうめき声があちこちから聞こえ、制服の背中がもぞもぞ動いている。さっきのひどい大音量のせいで気を失ったのだろうか。
「う、……ぅ……」
「……っく」
一人、また一人と目を開け、机に手をかけて身を引き起こそうとしている。くるみは僕の足下で苦しげに身をよじっている。助け起こそうかとかがみ込んだとき、緑色の烈しい光が僕の視界の上半分を灼いた。
「……ぅッ」
目を手で覆ってまぶたを閉じる。ところが信じがたいことに緑の光は視界から消えなかった。真っ暗闇の中で、変わらずそこにぎらついている。
なんだこれ?
目を開き、あちこちを見回す。どちらを向いてもその横長の緑の光帯は僕の視界の上半分、距離でいうと二メートルくらい先に浮かんでいた。眼球がどうかしてしまったのだ、と思った。後に、それが視神経に直接送り込まれた映像だとわかるのだが、そのときの僕には知るよしもなかった。とにかく気持ちを落ち着かせるので精一杯だったのだ。
光の帯は、よく見てみれば、文字だった。アルファベットだ。
RESTART THE GAME
そう読める。
……ゲーム再開……?
文字列が数万のドットに砕けたかと思うと、視界の隅に散って、ワイヤーフレームやごちゃごちゃとした数値表記の羅列に変わった。もう僕は混乱しきっていて、教卓にしがみついたまま口を半開きにし、視界に躍る数字やアルファベットや円や直線に見入っていた。
クラスメイトたちが起き上がる。男子の一人が毒づいた。
「……今日のリスタートは早ぇなおい、まだホームルーム中だぞ!」
べつのだれかが髪を掻きむしりながら言う。
「全員起きてるか?」「点呼!」「装備と残弾を確認しろ」「ちょっと待ってよ、前回のゲームから装甲値が変わってないよ、ひどい!」「いいからさっさと索敵しろって!」
剣呑とした言葉が飛び交う教室の黒板前で、僕は唖然としたまま立ち尽くす。いったいなにが起きているのかはまったくわからなかったが、僕以外のみんなはこの異常事態にどうやら慣れているらしいということだけわかった。
「ああッ」そばにいた男子の一人が僕の手元を見て素っ頓狂な声を上げる。「やっぱり藍沢がコマンダーだ」
「マジか」「やっぱりな」「学級委員がコマンダーって決まってるんだね」「やべえよ」
クラスメイトたちが寄ってきて僕を取り囲むので、僕は気圧されて後ずさる。
「藍沢、さっき笑ったりして悪かった!」「マジおまえが頼りなんだ」「藍沢さんって呼ぶから勘弁してくれ!」「コマンダーだって知らなかったんだよ、ほんとごめん」
男子たちのあまりの急変ぶりに僕は目を白黒させる。
「あ、あのっ、……コマンダー? ていうか、な、なにがどうなってんの?」
だれかが答えるよりも早く、校舎が大きく揺れた。耳障りな軋みが四方八方から押し寄せ、女子たちの小さな悲鳴が混ざる。地震?
「やばいって時間ないよ」と男子のだれかが言った。
「おい有間、藍沢を屋上に連れてけ、ついでに手っ取り早く色々説明しろ!」
「なんであたしがっ」とくるみが唇を尖らせる。
「出席番号2番だろ!」
「もーっ、けっきょくそれなのーっ?」
くるみは僕の左手首をつかんだ。そこで気づく。僕の視界の左上に、白熱する文字が浮かび上がっている。
1B Commander
司令官(コマンダー)――この一年B組の?
「ほら藍沢、行くよ!」
僕はまたも手を引きずられて廊下に出た。他のクラスの生徒たちもせわしなく廊下を駆けていくのが見えた。視界内の緑色の各種表示はまだ消えていない。ところどころ赤い文字が点滅しているのが不安を誘う。
「いい、藍沢、あんたはうちのクラスのリーダーなの! ぐだぐだ言ってないでさっさと状況を把握してちゃきちゃき働いてね!」
「……状況、って」
僕らは階段を駆け上がり、屋上へと出る重たい金属扉を押し開いた。
すでに何人もの生徒たちが屋上にいた。手すり越しに、どっぷりと曇った暗い空をじっとにらんでいる。僕もくるみに促され、手すりに近づき、眼下に広がる光景に息を呑んだ。
学校の敷地のすぐ外にあるはずの、家も道路も寺も墓地も商店街も竹林も雑木林も、なにもかもが消え失せていた。見渡す限りに広がっているのは、荒涼とした褐色の岩場だった。喉をこわばらせて視線を持ち上げ、首を巡らせる。どちらを向いても同じだ。地平線まで、岩だらけの荒野が続いている。
なんなんだ、これは。
僕の混乱は限界点に差しかかっていた。ひととき平衡感覚さえも消えかけていた。指一本で背中を押されるだけで真っ暗闇の中に転げ落ちていってしまいそうだった。
「あのね、藍沢」
くるみのひそめられた声が耳に引っかかる。すぐ隣にいるはずなのに、遠く聞こえる。
「先に言っとくけど、あたしらだってコレなにが起きてんのかよくわかってないの。でもはじめてじゃないの。このゲーム、ええと、もう六回目なの」
僕はくるみの横顔を見つめた。彼女は手すりの向こうに広がる荒れ地と曇天の接線をじっと凝視している。
「あんたも、このへんに――」とくるみは手を伸ばして自分の前を指さす。「色々見えてるでしょ、緑色の文字とか数字。燃料、兵器データ、それからレーダーサイト」
唾を飲み下し、うなずく。くるみにも見えてるのか。いや、他のみんなにも、か。
「ほんとに、なんでこんなゲームやらされてんのか、全っ然わかんないんだけど」
くるみの手がなにもない空間をまさぐった。と、彼女の指先で光る矩形が何度か明滅したかと思うと、次の瞬間、目を疑うことが起きた。くるみの手のひらに忽然となにか細長いバトン状のものが現れ、その両端が枝分かれしたりねじくれたり新しい被膜に覆われたりしながら伸び、彼女の身長とほとんど変わらないくらいの長さになったのだ。
彼女が握っている部分は、今や斜めに突き出したグリップとなっている。引き金に指がかけられる。
長大な、銃砲――だ。おそらく。金属ともプラスティックともつかない不思議な光沢の素材でできていて、奇妙なパーツがあちこちに装されているせいで、なんだか前衛美術の彫刻作品みたいだったけれど、全体から漂う威圧感は兵器が放つ特有の凶気だ。
なにもない空中から、たしかに現れたのだ。あり得ない。もう、目の前で起きているなにもかもが僕の常識をせせら笑っていた。
ゲーム。その響きだけが、かろうじて僕の現状と認識とをつなぐ。
くるみは砲身を手すりに置いて、砲口を垂れ込めた雲に向け、言葉を続ける。
「週に一回、放課後にいきなりこれが始まるの。学校中がこれに放り込まれてね。全滅させるまで戻れないわけ」
「……全滅?」
なにを?
気づけば、屋上にいた他の生徒たち――二年生も三年生もいる――もくるみと同じように空中から次々といかめしい機器を引きずり出して手際よく構えている。形状こそ、円盤状のものや両肩で支えるもの、全身をほとんど覆うようなもの、と様々だったけれど、素材や部品の細部がどれも共通していると一目でわかる。見た目に反して重量はあまりないのか、ただの高校生のはずの生徒たちが自分の身体と同じくらいの大きさの兵器を軽々と扱っていた。
ゲーム。ゲームだから……?
「反応あったぞ。方角227」とだれかが大声で言った。僕の視界内、右隅の方眼になった部分が急激にズームして地形をスキャンし始める。
「……でかいな」「全長18メートル、三体……か」
「いや四体目も確認した」「接近中?」「あと一分半てとこだ」
「すげえ速いな」「四体かよ……やれんのか」「前は二体でもかなり――」
張り詰めた言葉が屋上で飛び交う。僕らの頭上で雲が重苦しく北へと動いている。
接近中、って、なにがだ? 僕は自分の鼓動を痛いほど感じる。
「いーい、藍沢、あんたはうちのコマンダーなんだから絶対にやられないで」
くるみの平手が僕の背中に叩きつけられる。
「やられる、って……なにに」
彼女は地平線を指さした。
「なにかは、よくわかんないんだけど、あたしたちは――」
視界内に警告色のメッセージが躍る。兵器の安全装置が外れる音が一斉に響く。階下で生徒たちの足音と警戒を呼びかける声。
やがて――
それが地平に現れる。
最初は、白いしみのような影だった。みるみるうちに岩の大地の褐色と曇天の灰色とを食いつぶしながらそれは肥大化する。巨大ななにかがすさまじい速度でこちらに近づいてきているのだ、とわかった次の瞬間には、それは僕の眼前にそびえ、僕を圧し潰そうとするほどに視界を埋めていた。
四つ脚の獣にも、蜘蛛にも、百足にも、また這いずる人の姿にも見え、それらのどれでもなかった。剥き出しの筋と腱がぬらぬらと濡れてグロテスクに光っていた。多関節の肢は無秩序に胴から突き出て大地をえぐっていた。どこが頭なのかもわからなかったが、体表のあちこちに眼球とおぼしき器官が埋め込まれてぎろついていた。それを形容する言葉など、僕らはまったく持っていないはずだった。けれど。
ひとつだけ、あまりにも、あまりにも明確な、おぞましいくらい荘厳な外見的特徴を、それは有していた。見間違いようもなかった。胴の、おそらくは背にあたる部分から、天に向かって高く衝き伸ばされ、雲を払うかのように羽ばたいている――
一対の、真っ白な翼だ。
くるみが震える声で続けた。
「――天使、って呼んでる」
*
不登校寸前になったきっかけは、高校に入学してすぐにこじらせた風邪だ。二週間くらい休み、四月末に病み上がりで登校してみると、一年B組の教室はとても居づらい場所になっていた。授業には全然ついていけないし、体育の時間も僕だけペアの相手がいなかったし、教室移動の際にも不案内な僕だけがクラスに取り残された。もちろん、クラスメイトにノートを写させてもらうなり移動先を訊くなりすればいいだけの話だ。そもそも人に自分から話しかけることが苦手だった僕は、病気をしていなくてもいずれなにかしらの些細なきっかけで孤立していたのだろう。
とどめになったのは生物の時間だった。実験授業にはじめて出席したら、六人ずつの実験班がすでにできあがっていて、僕はどこの席に座ったらいいのかもわからなかった。
「ああ、藍沢は休んでたんだっけか?」と先生はのんびり言った。「それじゃあ、どこかの班にてきとうに混ぜてもらえ」
クラス全員が迷惑そうな顔を僕に向けてきた気がした。僕はトイレにいくと偽って生物室を出ると、そのまま戻らなかった。
それ以来、登校してもクラスに顔を出すのが気詰まりで、かといって不登校になってしまうほどの勇気も持てず、僕は図書室や裏庭で時間を潰すようになった。
陽当たりの悪い湿った土の上で、遠くチャイムを聴きながら弁当をもくもくと食べていると、中学のときとなにも変わっていないな、と情けなくなってくる。とくにいじめられていたわけでも無視されていたわけでもないけれど、どうしてもクラスになじめなかった。同級生たちが無言で僕を詰っているように思えてしかたなかった。なんでおまえはここにいるんだ、と。だから休み時間はトイレの個室にこもって本を読んだり音楽を聴いたりして過ごした。司書の先生がいないときには一日中図書室で時間を潰した。
高校でなにもかも心機一転やり直そうと、僕の中学からはまずだれも進学しなそうな東京の高校を無理して受けてやっとの思いで合格したというのに、けっきょく同じ繰り返しだ。考えてみれば当たり前だった。僕自身が変わっていないのに、僕を取り巻く世界がそう簡単に変わるわけはないのだ。
人生はゲームじゃない。ボタン操作ひとつでリセットはできない。これが、僕の生きてきた十五年間で学んだいちばん大切なことだ。
でも僕は間違っていた。人生は実にそのままの意味でゲームだった。
最悪なことに、リセットできない点に変わりはなかったけれど。
*
未咲と出逢ったのは、五月はじめの月曜日のことだった。どこかのクラスが図書室で自習だったので、居場所を追われた僕がふと思いついて北校舎の屋上にいってみたところ、先客がいたのだ。最初は彼女の存在に気づかなかった。剥き出しのコンクリートを踏む新鮮な感覚を味わい、手すりに近寄っていつもよりずっと広く見える空をぐるりと見渡し、眼下の校庭から聞こえてくるホイッスルと砂っぽい足音のリズムを聞くともなしに聞き、手すりに背を向けて寄りかかって大きく息をついたところでようやく気づいた。
階段室の屋根の上に、人影があった。僕はびっくりして後ずさった。女の子だ。うちの制服を着ているからにはうちの生徒なのだろうけれど、その目つきはなんだか高校生とは思えないくらい大人びていた。いや、大人びていたというのは正確な表現じゃない。もっと深くて厳しい、一切の生物の存在をゆるさない塩湖みたいに澄んだ眼だった。
だからだろう、僕はしばらく魅入られてしまった。
彼女はだいぶ前から僕に気づいてたらしく、身を低くして警戒の色もあらわにこちらをにらみ下ろしていた。長いすべらかな黒髪を無骨なまでに大きなヘッドフォンでおさえつけているせいで、人を寄せつけない雰囲気はいっそう際立っていた。
「……あ、ああ、ごめんなさい」
ようやく我に返った僕は言った。
「その、人がいると思ってなくて」
すぐに校舎内に戻るべきだったのだろうけれど、そのためには彼女の見ているすぐ真下を通過しなければならず、気詰まりで手すりを離れられなかった。
彼女はむっとした顔で階段室の屋根から飛び降りた。黒髪とスカートが春風にひるがえって大きく広がる。僕が気圧されて言葉を失っている間に、彼女はさっさと校舎に入っていってしまった。
扉がつっけんどんに閉められた後で、僕は大げさに息をつく。視線が合っている間まわりの音が聞こえなくなるくらいの強い瞳だった。
だれだろう、あれは。こんな時間に屋上にいたということは、僕と同じく授業をさぼっていたということだろうか。
ともかくこっちの校舎の屋上を使うのはやめよう、と僕はドアをくぐった。
でも彼女とは翌日すぐに再会することになった。南校舎の方の屋上なら大丈夫だろうと思って二時限目の終わりに行ってみたら、やはり階段室の上に黒い影がうずくまっていたのだ。膝を抱えてしゃがんでいた彼女は、身を乗り出してきて僕を見る。ヘッドフォンに挟まれた不機嫌そうな顔がむっとしかめられる。
「あ、あのっ、……ごめん」
僕はあわてて言った。
「こっちならいないかと思って、その」
彼女がまたも屋根から下りようとしたので僕は両手をばたばた振って制止した。
「い、いや、いいよ、僕がいなくなるから、ほんとごめん」
首が痛くなるくらい顔を伏せたままドアに飛び込んだ。少しでも視線を上げたら彼女の太ももとかスカートの中身が目に入ってしまいそうだったからだ。一階まで足を止めずに駆け下り、階段の裏側の埃っぽい空間に身を押し込んでようやく一息ついた。
屋上は彼女のテリトリーなのか。しかたない、あきらめよう。
三度目の遭遇も信じがたいことにその翌日だった。司書がいなかったので図書室で一日過ごそうと決め、最近お気に入りの怪奇小説のシリーズを読み進めようと棚を探したら、読み途中の三巻だけがなかった。しかたない、飛ばして読むか、と四巻を抜き取り、他にも何冊か選んで重ねて抱え、机の並ぶスペースに行ったら見憶えのある人物が座っていた。彼女だった。
あちらも驚いていたが僕の驚きはそれ以上だった。三日連続で顔を合わせたのもそうだが、彼女が読んでいたのがまさに僕が探していた三巻だったからだ。僕は口をぱくぱくさせて、自分の手の中の一冊と彼女の手元の一冊を何度も見比べる。彼女も気づき、むうっと唇をすぼめ、立ち上がった。
「この栞、ひょっとしてあなたの?」
はじめて聞く彼女の声だった。しばらく、それが僕に対する質問だということを理解できなかった。彼女がページの間から引っぱり出した細長い和紙片は、たしかに僕がついこないだ挟んでおいたものだ。
「……う、うん」と僕はうなずく。
「じゃあ早く読んじゃって」
彼女は本を僕の方に押しやってくる。
「いや、いいよ、先に読んでも」
というか僕は出ていくよ、と言いかけた僕を無視して彼女は本棚に向かった。僕は途方に暮れてしまう。このまま彼女の厚意――といっていいのかわからないが――に甘えてこの三巻を今ここで読むのもなんだか気が引けるし、かといってさっさと出ていくのも気持ちを踏みにじるみたいで失礼だし……。
ちらと彼女の様子をうかがう。そこで僕ははじめて、彼女がブレザーの左腕に巻いている赤い布帯に気づく。腕章だ。白抜きで『1C 学級委員』とプリントされている。学級委員なのか。ていうか授業しょっちゅうさぼってるくせに、どうして学級委員の腕章なんてちゃんと着けてるんだ?
と、そんな疑問がどうでもよくなるくらい重大なことに気づいた。さっきから彼女は本棚の同じ箇所を何度も何度も指でたどって探しているのだ。まさか、と思いつつも、僕は思いきって声をかけた。
「あの」
ヘッドフォンをしているから聞こえないかな、と心配したけれど、彼女はこっちを見た。
「ひょっとして、探してるの、これ?」
さっき一緒に持ってきた恋愛小説シリーズの二巻を持ち上げてみせる。自分でも読んでおいてなんだが、こんなべたべたに甘いのも読むのか、と意外に思った。彼女は目を見開き、頬を染めて横を向く。
「ち、ちがっ、そ、そんな恥ずかしいの読まない。だいたい主人公が鈍くていらいらするやつは大嫌い」
「読んでんじゃん」
思わず口に出してしまった。彼女は真っ赤になって、大股で図書室を出ていった。
僕は椅子に腰を下ろして頭を抱え、盛大に後悔した。怒らせてしまった……。たまに勇気を出して人に話しかけてみればこれだ。もう僕なんて一生無言でいた方がいいのかもしれない。いや、でも、今のって僕がなにか悪いのか?
まあいいや。とにかく結果的に図書室でひとりになれたんだ。続きを読むか。
ページをめくってはみるものの、彼女のことが気になって小説の内容なんてちっとも頭に入ってこなかった。あいつはなんなんだろう。僕と同じようにクラスになじめなくて授業にも出ずにひとりで時間を潰しているかわいそうなやつだろうか。あのつんけんした態度なら孤立するのも無理はない、自業自得だ。……と考えたところで、全部自分にも当てはまるので落ち込んできた。
1Cと腕章に書いてあったっけ。一年C組なら隣のクラスか。でもお互いにほとんど教室に顔を出していないとなれば見憶えがないのも当然だった。
それ以上彼女について考えていてもしかたがないので、僕はむりやり小説に意識を戻そうとする。でもなにかがまだ引っかかっている。一年C組。……C組?
たしかこの高校は一学年が二クラスずつじゃなかったか。C組なんてあったか?
*
翌日、他の生徒がまだ一人も登校していない早朝に、僕は登校した。南校舎二階、東側の階段から数えて三番目が僕の一年B組だ。その隣の教室には、室名プレートが掲げられていなかった。そうっと戸を引いて中を覗いてみる。ぎょっとした。教室は空っぽだった。
……いや、教壇の前にひとつだけ、机と椅子がぽつんと置かれている。
それだけだ。教卓もないし、掃除用具入れにはなにも入っていないし、黒板消しもチョークも見当たらないし、掲示板はまっさらだ。
おそるおそる足を踏み入れる。早朝の静けさがしんと肌に染みいってくる。
あらためて見回す。ほんとうに、机ひとつを除いてなにもない。壁際の床には埃がたっぷりたまっている。日焼けして変色したカーテンが束ねられもせずだらりとレールからぶら下がっている。黒板の粉受けはきれいなままだ。
なんだこの教室……。
机に近づいてみる。深緑色のファイルが一冊、のっている。出席簿だ、と気づく。
取り上げてめくってみると、四十いくつに行分けされたリストのいちばん上の欄にぽつんと一人分の名前だけが記されていた。
『七連坂 未咲』
しちれんざか・みさき。
これがあの女の子の名前なんだろうか。一人だけしか載っていない出席簿っていったいどういうことだ。
くだらない妄想が次々に湧き起こってくる。あいつ、ひょっとして幽霊じゃないか。ずっと昔、在籍数が多くて一年C組が存在した頃の生徒で、自殺かなんかで地縛霊になって学校をずっとうろついている、とか。あるいはもう少し現実的に、ひとりぼっちをこじらせすぎて、空き教室を使って自分だけのクラスを捏造した、とか――
背後で戸が開く音がして、僕は驚いて振り向いた。
戸口のところに彼女が立っていた。口を半開きにして僕を見つめ、それから首にかけていたヘッドフォンを急いで耳に着ける。
「なっ、なんでこんなところにいるの!」
視線をそらし、ぶっきらぼうな声で彼女は言った。
「あっ、ご、ごめん、勝手に入って」
憤然と歩み寄ってきた彼女は、僕の手から出席簿を引ったくると、『七連坂未咲』の名前の横、今日の日付の欄に丸印を書き込んだ。それから机に鞄を下ろす。
やっぱりこいつが七連坂未咲なのか。
「……あのう、ここって……空き教室、だよね?」
そうっと訊いてみた。七連坂未咲は首を振った。
「教室じゃない」
「……え?」
「ここは司令室」
ぽかんとした間があった。
言われたことが理解できなかった。シレイシツ、というその単語が頭の中でしかるべき漢字に変換されるのにかなりの時間を要した。
「……司令室? えっと、どういうこと?」
「わからないならいい」
七連坂未咲は首を振り、出席簿を持ったまま教室の戸口に向かおうとした。
いけない、昨日怒らせてしまったことをせめて一言でも謝らなければ、と僕は思い、どう言葉にすればいいのかも深く考えずに呼び止めていた。
「あ、あの、ちょっと待って」
未咲は足を止めて振り返った。露骨に不機嫌そうなので僕はたじろぐ。
「なに?」
訊かれ、答えに窮し、なんでもいいから言わなければと焦って口を開き、出てきたのはこんな言葉だった。
「……あのシリーズ、二巻からは主人公がちょっと鈍くなくなってるよ」
なに言ってんの僕? 謝るんじゃなかったのかよ?
しかし発した言葉を引っ込めることはできない。未咲は一瞬面食らった表情になり、それからぷいと横を向く。
「だからなんなの。あ、あんな甘ったるいの、読むわけない」
わざとらしいくらい足音を大きく響かせて未咲は廊下に出ていった。僕は様々な後悔にまみれて床にしゃがみ込んだ。
しかしその日の三時限目、図書室に行ってみたら、例の恋愛小説のシリーズは最終巻までごっそり貸し出し中になっていたので、ちょっと笑ってしまった。
*
そうしてすべてが始まる――あるいは終わる――水曜日がやってくる。水曜日は、校舎裏に積まれた廃棄予定の古い机に腰掛け、ぼんやり音楽を聴いて過ごすことにしていた。ちょうど曲の切れ目にチャイムの音が重なり、イヤフォンを外して時刻を見る。六時限目が終わるところだった。
さて家に帰るか、と机の山の上から降りようとしたときだった。
「あーっ、いた! 藍沢!」
やかましい女の声が耳に突き刺さり、僕は転げ落ちかけた。重なった机が軋んだ。校舎の角から姿を現し、こっちを指さして近づいてくるのは、髪を茶色く染めて制服の大胆に着崩した女子生徒だった。
「ほんッと捜したんだからね! サボるなら同じ場所でサボれっての、いつどこにいるかもわかんないんだから!」
「え、あ、あの?」
捜した? 僕を? ていうか――だれ?
「信じらんない!」とその女子生徒は目を見張る。「同じクラスなのに憶えてないの? あんたも三回か四回は授業出てるでしょぉ? あたし有間、後ろの席の! 有間くるみ!」
三回か四回で同級生の顔と名前が一致するようなまともな人間なら、今ごろ僕はこんな場所でサボってたりしない。
「ほんっとに憶えてないの? こんな可愛くて読モまでやってて最近マスカラも思い切ってパール入りに変えちゃったくるみさんを憶えてないの?」
「初対面のときにその痛い自己紹介やってくれてたら憶えてると思うけど」
「なんだと」と彼女は僕の襟首をねじり上げた。細腕に見合わず怪力だった。「痛いんじゃないの、こういうキャラ作りがティーン誌では受けるの!」
「ごめん、ごめんってば!」
僕、どうやら胸の内にしまっておけばいいことをぽろっと漏らす癖があるらしかった。未咲にもそれで怒られたし、人と喋っていないとこういう悪癖も治らないまま成長しちゃうのか、と暗い気持ちになる。
「って、こんなことしてる場合じゃなかった。早く来て、この後ホームルームなんだから! 今まで学級委員がいなくて全然なんにも話が進まなかったんだからね!」
「……学級委員?」
有間くるみは、答えるよりも早く僕の左腕をつかむと、なにか赤いものを取り出して巻きつけてきた。
「な、なにっ?」
「暴れるなっての、安全ピン刺さるよ!」
腕章だった。『1B 学級委員』という文字が白く染め抜いてある。未咲がつけていたものと同じだ。
「……なんで僕が学級委員なの?」
「委員決めるときに休んでたでしょ。だからみんなやりたがらなくて押しつけたの」
僕は天を仰いだ。横暴にもほどがある。くるみは僕の手首をつかんでずんずん歩き出した。僕は足下に置いてあった鞄をあわてて取り上げると、彼女の手の感触にどぎまぎしながらもついていく。引っぱらなくても歩ける、という言葉さえ口にする勇気が持てない。二階の1B教室にたどり着くまでの間、すれちがう他の生徒たちの視線が痛かった。
「藍沢見つけた、連れてきたよ!」
くるみは教室の戸を開けてそう言うと、僕を中に引きずり込んだ。たちまち視線が集まり、僕の身はすくみあがる。まばらな机と、十数人の男女たち。僕を見る目は不審と不安と猜疑と好奇が四分の一ずつだった。僕の被害妄想かもしれないけれど。目を伏せると、視界の端、教壇の隅で担任教師がパイプ椅子に座って苦笑しているのが見えた。まだ赴任してきたばかりの若い女の先生だ。僕が授業に出ていないのを知っていてもなにも言ってこない内気そうな人だから、この場でもたぶんなんの助けにもなってくれないだろうな、と思う。
「……藍沢?」「へえ、学校には来てたんだ」「何度か見たよトイレとかで」
クラスメイトたちが交わす言葉の端々が聞こえてきて、僕は真剣に逃げ出すことを検討し始める。でもくるみが僕の背中をずいずいと押して教壇の向こう側に立たせる。
「生徒会に怒られちゃったんだから、うちのクラスだけ学級委員が全然働いてなくて決めるものも決めてないって! 今日のホームルームはあんたがちゃんと仕切ってよ!」
「い、いや」
僕は言い返そうとして咳き込む。みんなから注がれる視線に憐れみが混じり出す。
「仕切れって言われても、なにやればいいのか」
「いいから早く始めろよ学級委員」「俺さっさと済ませて部活行きたいんだよ」「あたしも」
野次が飛び、僕はまたも顔を伏せてしまいそうになる。
「でも、あの」からからの声をなんとか押し出す。「まだクラス全員集まってないみたいだから、その」
なんとか時間を稼ぎたい一心で言った。でも、教卓のすぐ近くの席のくるみも、教壇の脇の先生も、そしてクラスメイトたちも、怪訝そうな顔になる。
「そろってるよ」とだれかが言った。
「サボってたのはおまえだけだよ」とべつのだれかが言い、笑い声がいくつもあがる。
僕は身をすくませながらも教室を見回す。だって、どう見ても十何人しか――
そこで気づく。
机が足りている。
くるみの前の空席は、彼女の話からして僕の席だろう。そのひとつを除いて、すべての椅子に生徒が着席している。全員、そろっている……? 目で生徒を数える。十六人だ。
「うちは十六人学級だよ」「授業出てないからって、だいたいの人数くらいわかるでしょ」
「そ、そうなんだ」
僕は出てもいない額の汗を拭うふりをした。十六人学級? そんなに少なかったか? おかしい。憶えている限りでは、普通に四十人弱はいたはずだ。いくら僕が入学直後からほとんどクラスに顔を出していないといっても、倍以上も数を勘違いするものだろうか。
「だから早く始めろってば」
「もーっ、しゃあないから手伝うよ」とくるみがげんなり顔で立ち上がった。「あたしが黒板書くから、藍沢はほら、そこ、議題がファイルにまとめてあるよ」
「あ、う、うん」
「くるみが最初から学級委員やればよかったんじゃないの」
女子生徒のだれかが冷やかした。
「やだよ! 中学でずっと出席番号1番で、色々雑用押しつけられてきたんだから」とくるみは口を尖らせる。「せっかく藍沢がいるんだから全部押しつけるの!」
出席番号1番だから僕は学級委員にさせられたのか、と絶望的な気分になる。それじゃあ委員決めの日にたとえ出席していたとしても、どうせこうなる運命だったってことか。
しかたない。
教卓の上に置いてある『1B』というラベルの貼られた水色のファイルに目をやる。なにをどうすればいいのかはよくわからないけれど、とにかくこの場をなんとか切り抜けてさっさと帰ろう、そして明日から完全に不登校になるべきか検討しよう――と、ファイルをつかみ上げた、その瞬間だった。
チャイムが鳴るのが聞こえた。
メロディこそ同じだけれど、ひどく不愉快に割れた響きだった。しかも、一打ちごとに音が大きくなってきている。僕はなにごとかとスピーカーを見やる。クラスメイトたちも表情をこわばらせてあたりを見回している。頭痛がしてきた。頭蓋骨をハンマーで直接叩かれているみたいだ。両手で耳をふさいでも音量は堪えがたいほどになり、僕は歯を食いしばって教卓に突っ伏した。なんだこれ? なにが起きてるんだ?
チャイムが止んだ。
僕は顔を上げる。
骨の内側でまだ痛みが反響していて、頭がくらくらしていた。目もいくぶんかすんでいて、あたりが薄暗く見える。……いや、ほんとうに薄暗いのか。窓ガラスの向こうの空がどんより灰色に塗りつぶされている。さっきまで晴れていたはずなのに。
クラスメイトたちはみんな椅子からずり落ちたのか机の間の床に倒れていた。かすかなうめき声があちこちから聞こえ、制服の背中がもぞもぞ動いている。さっきのひどい大音量のせいで気を失ったのだろうか。
「う、……ぅ……」
「……っく」
一人、また一人と目を開け、机に手をかけて身を引き起こそうとしている。くるみは僕の足下で苦しげに身をよじっている。助け起こそうかとかがみ込んだとき、緑色の烈しい光が僕の視界の上半分を灼いた。
「……ぅッ」
目を手で覆ってまぶたを閉じる。ところが信じがたいことに緑の光は視界から消えなかった。真っ暗闇の中で、変わらずそこにぎらついている。
なんだこれ?
目を開き、あちこちを見回す。どちらを向いてもその横長の緑の光帯は僕の視界の上半分、距離でいうと二メートルくらい先に浮かんでいた。眼球がどうかしてしまったのだ、と思った。後に、それが視神経に直接送り込まれた映像だとわかるのだが、そのときの僕には知るよしもなかった。とにかく気持ちを落ち着かせるので精一杯だったのだ。
光の帯は、よく見てみれば、文字だった。アルファベットだ。
RESTART THE GAME
そう読める。
……ゲーム再開……?
文字列が数万のドットに砕けたかと思うと、視界の隅に散って、ワイヤーフレームやごちゃごちゃとした数値表記の羅列に変わった。もう僕は混乱しきっていて、教卓にしがみついたまま口を半開きにし、視界に躍る数字やアルファベットや円や直線に見入っていた。
クラスメイトたちが起き上がる。男子の一人が毒づいた。
「……今日のリスタートは早ぇなおい、まだホームルーム中だぞ!」
べつのだれかが髪を掻きむしりながら言う。
「全員起きてるか?」「点呼!」「装備と残弾を確認しろ」「ちょっと待ってよ、前回のゲームから装甲値が変わってないよ、ひどい!」「いいからさっさと索敵しろって!」
剣呑とした言葉が飛び交う教室の黒板前で、僕は唖然としたまま立ち尽くす。いったいなにが起きているのかはまったくわからなかったが、僕以外のみんなはこの異常事態にどうやら慣れているらしいということだけわかった。
「ああッ」そばにいた男子の一人が僕の手元を見て素っ頓狂な声を上げる。「やっぱり藍沢がコマンダーだ」
「マジか」「やっぱりな」「学級委員がコマンダーって決まってるんだね」「やべえよ」
クラスメイトたちが寄ってきて僕を取り囲むので、僕は気圧されて後ずさる。
「藍沢、さっき笑ったりして悪かった!」「マジおまえが頼りなんだ」「藍沢さんって呼ぶから勘弁してくれ!」「コマンダーだって知らなかったんだよ、ほんとごめん」
男子たちのあまりの急変ぶりに僕は目を白黒させる。
「あ、あのっ、……コマンダー? ていうか、な、なにがどうなってんの?」
だれかが答えるよりも早く、校舎が大きく揺れた。耳障りな軋みが四方八方から押し寄せ、女子たちの小さな悲鳴が混ざる。地震?
「やばいって時間ないよ」と男子のだれかが言った。
「おい有間、藍沢を屋上に連れてけ、ついでに手っ取り早く色々説明しろ!」
「なんであたしがっ」とくるみが唇を尖らせる。
「出席番号2番だろ!」
「もーっ、けっきょくそれなのーっ?」
くるみは僕の左手首をつかんだ。そこで気づく。僕の視界の左上に、白熱する文字が浮かび上がっている。
1B Commander
司令官(コマンダー)――この一年B組の?
「ほら藍沢、行くよ!」
僕はまたも手を引きずられて廊下に出た。他のクラスの生徒たちもせわしなく廊下を駆けていくのが見えた。視界内の緑色の各種表示はまだ消えていない。ところどころ赤い文字が点滅しているのが不安を誘う。
「いい、藍沢、あんたはうちのクラスのリーダーなの! ぐだぐだ言ってないでさっさと状況を把握してちゃきちゃき働いてね!」
「……状況、って」
僕らは階段を駆け上がり、屋上へと出る重たい金属扉を押し開いた。
すでに何人もの生徒たちが屋上にいた。手すり越しに、どっぷりと曇った暗い空をじっとにらんでいる。僕もくるみに促され、手すりに近づき、眼下に広がる光景に息を呑んだ。
学校の敷地のすぐ外にあるはずの、家も道路も寺も墓地も商店街も竹林も雑木林も、なにもかもが消え失せていた。見渡す限りに広がっているのは、荒涼とした褐色の岩場だった。喉をこわばらせて視線を持ち上げ、首を巡らせる。どちらを向いても同じだ。地平線まで、岩だらけの荒野が続いている。
なんなんだ、これは。
僕の混乱は限界点に差しかかっていた。ひととき平衡感覚さえも消えかけていた。指一本で背中を押されるだけで真っ暗闇の中に転げ落ちていってしまいそうだった。
「あのね、藍沢」
くるみのひそめられた声が耳に引っかかる。すぐ隣にいるはずなのに、遠く聞こえる。
「先に言っとくけど、あたしらだってコレなにが起きてんのかよくわかってないの。でもはじめてじゃないの。このゲーム、ええと、もう六回目なの」
僕はくるみの横顔を見つめた。彼女は手すりの向こうに広がる荒れ地と曇天の接線をじっと凝視している。
「あんたも、このへんに――」とくるみは手を伸ばして自分の前を指さす。「色々見えてるでしょ、緑色の文字とか数字。燃料、兵器データ、それからレーダーサイト」
唾を飲み下し、うなずく。くるみにも見えてるのか。いや、他のみんなにも、か。
「ほんとに、なんでこんなゲームやらされてんのか、全っ然わかんないんだけど」
くるみの手がなにもない空間をまさぐった。と、彼女の指先で光る矩形が何度か明滅したかと思うと、次の瞬間、目を疑うことが起きた。くるみの手のひらに忽然となにか細長いバトン状のものが現れ、その両端が枝分かれしたりねじくれたり新しい被膜に覆われたりしながら伸び、彼女の身長とほとんど変わらないくらいの長さになったのだ。
彼女が握っている部分は、今や斜めに突き出したグリップとなっている。引き金に指がかけられる。
長大な、銃砲――だ。おそらく。金属ともプラスティックともつかない不思議な光沢の素材でできていて、奇妙なパーツがあちこちに装されているせいで、なんだか前衛美術の彫刻作品みたいだったけれど、全体から漂う威圧感は兵器が放つ特有の凶気だ。
なにもない空中から、たしかに現れたのだ。あり得ない。もう、目の前で起きているなにもかもが僕の常識をせせら笑っていた。
ゲーム。その響きだけが、かろうじて僕の現状と認識とをつなぐ。
くるみは砲身を手すりに置いて、砲口を垂れ込めた雲に向け、言葉を続ける。
「週に一回、放課後にいきなりこれが始まるの。学校中がこれに放り込まれてね。全滅させるまで戻れないわけ」
「……全滅?」
なにを?
気づけば、屋上にいた他の生徒たち――二年生も三年生もいる――もくるみと同じように空中から次々といかめしい機器を引きずり出して手際よく構えている。形状こそ、円盤状のものや両肩で支えるもの、全身をほとんど覆うようなもの、と様々だったけれど、素材や部品の細部がどれも共通していると一目でわかる。見た目に反して重量はあまりないのか、ただの高校生のはずの生徒たちが自分の身体と同じくらいの大きさの兵器を軽々と扱っていた。
ゲーム。ゲームだから……?
「反応あったぞ。方角227」とだれかが大声で言った。僕の視界内、右隅の方眼になった部分が急激にズームして地形をスキャンし始める。
「……でかいな」「全長18メートル、三体……か」
「いや四体目も確認した」「接近中?」「あと一分半てとこだ」
「すげえ速いな」「四体かよ……やれんのか」「前は二体でもかなり――」
張り詰めた言葉が屋上で飛び交う。僕らの頭上で雲が重苦しく北へと動いている。
接近中、って、なにがだ? 僕は自分の鼓動を痛いほど感じる。
「いーい、藍沢、あんたはうちのコマンダーなんだから絶対にやられないで」
くるみの平手が僕の背中に叩きつけられる。
「やられる、って……なにに」
彼女は地平線を指さした。
「なにかは、よくわかんないんだけど、あたしたちは――」
視界内に警告色のメッセージが躍る。兵器の安全装置が外れる音が一斉に響く。階下で生徒たちの足音と警戒を呼びかける声。
やがて――
それが地平に現れる。
最初は、白いしみのような影だった。みるみるうちに岩の大地の褐色と曇天の灰色とを食いつぶしながらそれは肥大化する。巨大ななにかがすさまじい速度でこちらに近づいてきているのだ、とわかった次の瞬間には、それは僕の眼前にそびえ、僕を圧し潰そうとするほどに視界を埋めていた。
四つ脚の獣にも、蜘蛛にも、百足にも、また這いずる人の姿にも見え、それらのどれでもなかった。剥き出しの筋と腱がぬらぬらと濡れてグロテスクに光っていた。多関節の肢は無秩序に胴から突き出て大地をえぐっていた。どこが頭なのかもわからなかったが、体表のあちこちに眼球とおぼしき器官が埋め込まれてぎろついていた。それを形容する言葉など、僕らはまったく持っていないはずだった。けれど。
ひとつだけ、あまりにも、あまりにも明確な、おぞましいくらい荘厳な外見的特徴を、それは有していた。見間違いようもなかった。胴の、おそらくは背にあたる部分から、天に向かって高く衝き伸ばされ、雲を払うかのように羽ばたいている――
一対の、真っ白な翼だ。
くるみが震える声で続けた。
「――天使、って呼んでる」